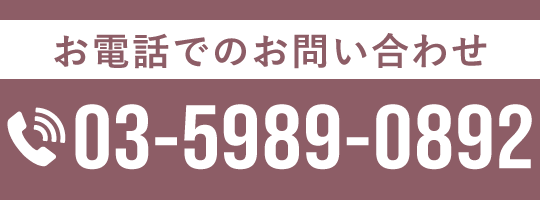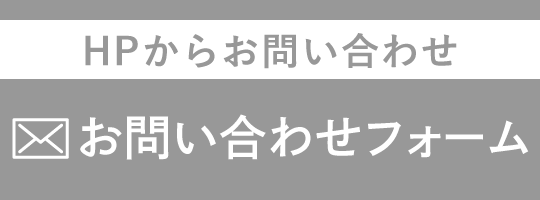Archive for the ‘身体的な被害’ Category
加害者との被害弁償・示談交渉の進め方について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします

犯罪の被害に遭ったとき、加害者との被害弁償・示談交渉はどのように進めていけばいいのでしょうか?
知り合いとの金銭トラブルの延長上の事件などであれば、お金や物さえ戻ってくればいいという人もそれなりに多いかと思います。しかし、見ず知らずの人に無理矢理わいせつな行為をされた場合等に関しては、すぐに示談をしようと考えるとは限らず、どのように交渉を進めていったらよいのか分からない人も多いと思います。
そこで今回は参考事例を基に、示談交渉の進め方を紹介していきたいと思います。
今回は、不同意わいせつ致傷事件の事例を参考にして解説します。
1 参考事件
愛知県内に住む女性のAさんは、ある日の夜10時頃、会社から帰るために道を歩いていたところ、いきなり暴漢に襲われ、胸を揉まれる、服の中に手を入れられる、抱きつかれるなどのわいせつ行為をされ、何とかそこから逃げ出すために抵抗をしました。何とか暴漢から逃れることはできましたが、暴漢から離れるときに転んでしまい、膝に全治2週間程度のケガをしてしまいました。Aさんはすぐに警察に通報したので、付近の防犯カメラなどがスムーズに回収でき、暴漢は逮捕されました。
暴漢が逮捕された知らせが入ってから2日後、暴漢の弁護人から、賠償金の支払いや示談の話がしたいと言われました。弁護人からは、今すぐに示談に応じてくれるのであれば示談金として100万円を支払いたい、というようなことを言われています。
示談に応じると今後どうなるかよくわからなかったのもあり、Aさんはインターネットで弁護士を検索して相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 示談で得られるもの
そもそも示談書に記載される条項は、①事実の特定②示談金③接触禁止④事件について示談後にお互い新たな主張をしないこと⑤犯人を許すこと、等の条項などが盛り込まれることが多いです。このうち、被害者側が示談をすることによるメリットは、②あるいは③になってくるでしょう。接触しない、ということについては当然と言う方もいますし、そもそも確実に担保されるかどうかもわからないという方も多いと思うので、明確な示談のメリットとしてはやはり示談金ということになるかと思います。本来、損害賠償金を得るためには民事裁判を起こして勝訴判決を得て、加害者の財産に執行をかけて回収をする等しなければならないわけですが、その損害賠償を示談の形ですぐに実現できるのも示談で得られる大きなメリットの一つです。
以下は、ひとまず、示談さえできれば基本的に示談金は直ぐに手に入ること、を示談の最大のメリットとして話を進めていきます。
3 注意したい点
まず注意したいのは、加害者側からの最初の示談金の提示は低めの金額に止まることが多いことです。実際に犯人側にお金があるか、誰がお金を出すかなど事情は様々で、相手方の弁護士が被害者側をだまそうとしていると言い切ることはできないのですが、本当に妥当な金額なのかはよく考えた方がよいです。
次に注意したいのは、示談の際に上記⑤の犯人を許す条項の追加を求められることが多い事です。たしかに、⑤のような条項を入れることによって、示談金の上乗せや、③のような条項の充実を図ることはできますが、犯人を処罰したい気持ちが強い場合は、⑤のような条項を入れるかどうかは慎重に考えた方がよいです。
最後に注意したいのは、犯人側から、すぐに示談をするように迫られることも多い事です。早く決めてください、と直接的に言われることはあまりありませんが、「検察官の処分もあるので」というようなことを電話口などで言われる可能性があります。それは犯人側の事情であって被害者側には何も関係ないのであり、検察官の処分期限があるのを良いことに示談金を抑えて示談も早く終わらせようという考えで言っている可能性があります。
しかし、示談が出来なければ今後も身体拘束が続く可能性が高く、刑事裁判にかけられて前科が付いてしまう可能性も高いわけですから、早めに示談をした方が示談金としては高い金額を得ることができる可能性は上がります。逆に、起訴されてしまって前科が付くことが確定したような場合、もはや今後示談の提案がなされることはなく、最悪1円も損害賠償金を得ることができなくなってしまうかもしれません。
そのため、被害者側として示談を行っていくにもタイミングを考える必要はあります。
ただし、起訴がされる前でさえあればまだ高額の示談金を支払うメリットはありますから、示談金を得たい気持ちが強くてもすぐに示談に応じる必要性は比較的薄いです。また、今回のような不同意わいせつ致傷の事案だと、示談をしない場合刑務所に行かなければならない可能性もありますから、裁判になった後でも比較的高額の示談金を得られる可能性があります。
上記のように、示談金の金額と、加害者側の処罰や身体拘束の長さについてはある意味トレードオフの関係にあります。示談金と、加害者側の事情については、刑事事件の知見が無ければ精度の高い計算を行うことは難しいでしょう。また、加害者側の弁護士も、刑事事件の様子を見て示談の動きを決めるわけですから、実際の事案に即した示談戦略は、刑事事件の経験が多い弁護士の方が精度が高くなると言えます。
4 弁護士による被害者支援
本件では、上記のように示談が無ければ加害者が刑務所に行く可能性が高い事件であると言えます。
そのため、比較的早い段階で示談に応じることで示談金の上乗せを狙っていくのか、あるいは示談のタイミングを遅らせて示談金と処罰のバランスを図っていくのか、というところがポイントになるかと思います。
多くの示談金を得たいのであれば早い段階から密な示談交渉を行い、バランスを重視するのであれば示談のタイミングを見極める方にエネルギーを注ぎます。
もちろん、被害者であれば、示談金でも処罰でもどちらも妥協したくない、トレードオフを受け入れるなどおかしい、というお気持ちになるのも十分わかります。当事務所では、経過に合わせて説明も詳細に行いますし、出来る限り示談金も処罰も最大限のものが得られるように尽力いたしますので、安心してご相談ください。
5 最後に
性犯罪その他の犯罪に遭われた方、被害弁償・示談交渉の進め方がよくわからない方、自分で事件の対応をするのがつらい方、示談をするなら納得いく条件で示談をしたい方、そもそも示談をすることが良いのかどうか分からないという方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。そもそも、トラブルに巻き込まれたために頭が整理が出来ておらず、何をしたらよいのかという考えにも至らない方もいらっしゃると思います。そのような場合でも、最大限お話を聞いて、最適な解決策を提案いたします。
相談に関しては無料ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
【事件解説】高校生失明、警察官を業務上過失傷害で起訴
沖縄県で起きた警察官が高校生を失明させてしまい業務上過失傷害罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】
沖縄県警の巡査Aが、沖縄市内の路上で、男子高校生Vが運転するバイクを止めようと、警棒を持った右手を差し出して警棒を高校生の右目付近に差し出して警棒を高校生の右目付近にぶつけ、右眼球破裂や顔面骨折などの大けがを負わせた。
【報道の概要】
報道によると、警察は巡査Aについて、「特別公務員暴行陵虐致傷」の容疑で那覇地方検察庁に書類送検していたが、検察庁は「故意」を十分に立証できないと判断して「業務上過失傷害」に罪名を変更して起訴したということです。
現場に防犯カメラはなく、目撃者もいませんでしたが、警察は専門家への聴き取りや実験などで一連の行為に故意があると結論付けていました。
しかし、那覇地検は故意が十分に立証できなかったとして「注意義務を怠り、警棒を目の前に差し出すなどしたことを過失と捉えた」としているようです。
被害者のVやその家族は、「バイクを走行させていたところに、物陰から突然飛び出してきた警察官に警棒で殴られたと認識している。怪我も重傷で、相当強い力で殴られたことは明らか。たまたま手に持っていた警棒が過失によって当たったとは考えられず、公判請求の罪名には納得できない。」とコメントしている。
(朝日新聞DIGITAL2023年6月29日の記事https://www.asahi.com/articles/ASR6Y6RCVR6YUTIL019.htmlより抜粋)
【判決の概要】
本事件については、令和5年12月25日に那覇地裁で判決が出ています(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/092645_hanrei.pdf)。
判決ではAに対して罰金100万円が科されています。なお、検察官の求刑も罰金100万円でした。
判決文によれば、Aは夜間職務質問時において必要とされている機材を適切に用いることなく、バイクで進行してくるVに「おい、止まれ」と声を発しただけで進路上に入り、漫然と警棒を持った右手をVの方に差し出したという行為が、重大な傷害結果を発生させる危険性が高い行為であり、警察官の基本的な注意義務にも反するものといえるため、Aは強く非難されるとし、傷害結果も右目失明など重大であると認定しています。
しかし、Vの方も、進路前方にいるAを、自身に対する職務質問を行うため停止を求めている警察官と認識し、停止又は徐行するなどの衝突回避等の措置をとれた可能性は否定できないとして、Aの過失だけが本件の重大な結果を生じさせたものとは言えないとして、懲役刑ではなく罰金刑にすることも許される事案と述べています。
その上で、AがVに対して謝罪の言葉を述べ、損害賠償金として100万円を供託するなど反省の態度を示していることも考慮し、業務上過失傷害の罰金上限である100万円に処するのが相当と判断したとしています。
【解説】
①特別公務員暴行陵虐致傷(刑法196条)
本件で警察が書類送検した「特別公務員暴行陵虐致傷」は、警察官が捜査対象者に暴行などを加えて怪我をさせたときに成立する罪で、15年以下の懲役刑に処されることになります。
この罪が成立するためには、捜査対象者に暴行を加えようとする意思、つまり暴行の故意が警察官にあることが必要となります。
今回の事件で検察庁は、Aが意図的にVに当てようと思って警棒を突き出したということが証明できないと判断して、「特別公務員暴行陵虐致傷」の故意が立証できないとしているといえます。
もっとも、V側がコメントしているような事情があれば、「特別公務員暴行陵虐致傷」の故意が認められると考えられますが、今回は防犯カメラや目撃者など客観的に故意を立証できる証拠がなかったために、検察庁は争われてしまうと負けてしまうと考えて罪名を変更したと考えられます。
②業務上過失傷害(刑法211条)
本件で起訴された「業務上過失傷害」は、業務上必要な注意を怠った過失によって人に傷害を負わせてしまった時に成立する罪で、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
「特別公務員暴行陵虐致傷」と比べて懲役刑の上限がかなり下がり、さらに罰金刑もある点で大きな違いがあります。
これは、故意による犯罪か、過失による犯罪かという点、つまりあえて行ったのか不注意でやってしまったのかという点による違いといえます。
今回の判決では、懲役刑ではなく、罰金刑の上限額である100万円の罰金刑が科されています。
③刑事裁判と民事裁判
今回の事件では、刑事裁判でAは有罪となり、罰金刑を受けています。
しかし、罰金は国に対して支払われるため、Vに対してはこの裁判によって金銭が支払われることはありません。
Vが治療費や失明してしまったことの慰謝料など、金銭的な賠償を受けたいと思う場合には、別途民事裁判を起こす必要があります。
民事裁判では刑事裁判と違って、訴える側(原告)が被害が発生した原因や被害の内容、損害賠償の額などを証明する必要があり、時間も労力もかかってしまいます。
そのため、多くの場合には示談や和解といった任意交渉で賠償を求めていくことが多くなります。示談についてはこちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
【公務員によって被害を受けた場合には】
公務員から被害を受けた場合には、懲役刑や禁錮刑の判決が下されるとたとえ執行猶予がついたとしても公務員としての身分を失ってしまうため、処罰を軽くするために示談交渉の打診があることが多いと思います。
示談を受けるべきか否かや、示談を受けた場合に公務員に下される処分がどうなるか、報道されるのかどうかなど、様々な疑問や不安が生じてくることと思いますので、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスをもらうことで、自分の希望を叶えるにはどうすればよいのか明確になりますし、弁護士に依頼すれば窓口になって交渉してくれるので精神的にも安心することができます。
傷害事件の被害者になったら
事件に巻き込まれて、傷害事件の被害者になってしまった場合について、解決策として、取りうる法的手段方法についてまとめました。

【先決事項】
まず、受傷をした状態から、元の健康な身体状況を取り戻すために、きちんと医療機関に受診して、適切な治療を受けて十分な身体の回復をはかりましょう。これがまず第一になすべき事柄です。その対応ができてからでも法的解決を図ることは、ごく普通に出来ますので、心配はいりません。身体の状態が思わしくないに慌てて行動した結果、怪我をした受傷状態が重くなるなどの事態は避けなければなりません。
そして、医療機関に関わりった際、治療費、薬代、病院等医療機関への自宅からの交通費(往復)も損害となり得るので、これらの損害については、賠償請求する際には、証拠として明らかにする必要があるため、支払った金銭の領収書類は、なくさないようにすべて保管しておきましょう。
【刑事事件化する場合】
次に、傷害事件として受傷事実に関し、これを刑事事件とするか、しないかを検討しましょう。
一人でどうして良いか分からない場合には、家族、親しい友人等に相談するのも方法ですが、適切な解決には、法的観点からの具体的アドバイスを受ける必要があることからすれば、専門家としての弁護士等に相談することが有効です。弁護士に相談すると費用負担が心配だと考える方も多いですが、最近では、弁護士による無料の法律相談や行政の窓口における無料相談なども広く行われており、インターネットを用いて、これらの情報検索をすることにより弁護士との接点も見つけることが可能となっており、利用することがおすすめです(犯罪被害に遭ってしまった場合に弁護士を依頼することのメリットはこちらにもまとめてあります。https://higaisya-bengo.com/bengosi_irai_meritto/)。
そして、刑事事件とする場合には、警察への被害申告として、被害届の提出が必要となります。被害届の提出と傷害の事実を証明するための診断書の提出は、初めての人であってもそれほど難しくはありませんので自分ですることもできます。診断書は診療を受けた医療機関に申し出れば作成してもらえます。
被害届を警察に出すと、通例、警察により、加害者としての被疑者(犯人)に対して、捜査が開始されることになります。
被害者の中には、被疑者との人間関係を気にして、被害届を出すことをためらう向きもあると思いますが、被害届を出すことにより、被疑者がどうなるかについて具体的に知れば、この点はある程度解決できるものと思われます。
【被疑者の受ける捜査とは】
被疑者に対しては、警察が、身柄拘束として逮捕する場合としない場合とに分かれます。逮捕されると、通例、検察官により被疑者の勾留請求がなされ、これを裁判所が認めると、一律10日間の身柄拘束が継続します。さらに勾留は10日間迄を限度として延長される可能性があります(逮捕・勾留についてはこちらもご参照ください。https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/)。勾留中は、当然、被疑者は身体拘束により刑事施設の中にいる状態となり、外部に出ることはできず、それまでなされていた社会生活は停止した状態となります。被疑者は、仕事や学校に行けなくなり、解雇や退学といった処分を受ける可能性もあります。
勾留が終わると、起訴不起訴の処分がなされて、起訴されれば裁判所の刑事裁判を受け、最終的には、必ず有罪無罪のいずれかの判決を受けて裁判の結果を受け入れることになります。
これが、警察に被害届を出し、逮捕が執行された場合の捜査から公判へと発展したときの典型的な手続きの流れになります。
これに対し、被害者は、被告人(被疑者が起訴されると被告人と名称が変わります。)の裁判手続に、証人として、被害を受けた状況を証言したり、裁判所に、被害者としての心情を訴えたり、さらには、刑事裁判の一当事者として法廷に参加して被告人に質問したりすることが可能となります(被害者参加)。また、刑事事件の法廷において、傷害による損害賠償を和解として解決する手続もあります。
【刑事事件化しない場合】
これに対して、被害届を出さなければ、事件化されないことから、通例、刑事裁判にはなりません。この場合、被害者が受けた傷害の結果等々の諸々の損害については、民事上の裁判手続等により解決が図られることになります。
【ぜひ法律相談を】
被害届を出すとその後の手続きは、おおむね上記のとおりです。悩みが解決せずに苦しむ日々を長引かせるのはよくありません。ぜひ、弁護士の法律相談を受け、心の中の不全感を解消しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では,被害者に特化した相談を受け付けています。初回の相談は無料ですので、傷害事件の被害に遭ってしまった場合は、まずは弊所までご相談ください。