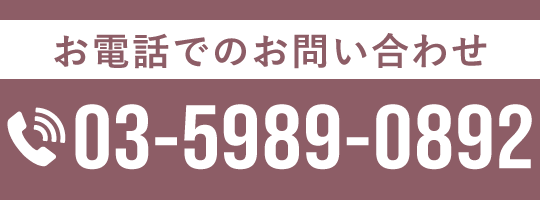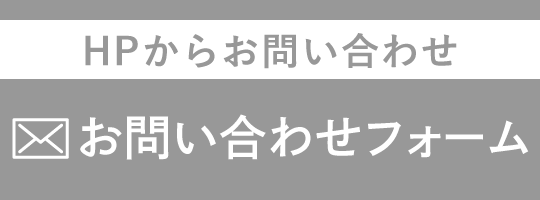Archive for the ‘犯罪被害者支援’ Category
【報道解説】盗撮未遂容疑の警察官を不起訴処分 女子中学生スカート内にスマホ疑い
警察官が女子中学生のスカート内にスマホを差し入れ盗撮しようとした事件について、不起訴処分となったという報道がありました。なぜ不起訴処分となったのかなどについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道の内容】
京都地検は、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)と京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された警察官Aについて、不起訴処分にした。理由は明らかにしていない。
Aは、京都市左京区の京阪出町柳駅で、スマートフォンを女子中学生のスカート内に差し入れ、撮影しようとしたとして、京都府警下鴨署に逮捕された。逮捕時の調べに対し容疑を認めていた。
(京都新聞令和6年2月14日インターネット記事https://news.yahoo.co.jp/articles/4bc2b7bed8a8011b6cd81fa1eb77038fb33701a5より抜粋。一部改変)

性的姿態撮影処罰法とは
性的姿態撮影処罰法とは、令和5年7月13日より施行された新しい法律です。
盗撮事件の増加に伴い、これまで各都道府県の迷惑行為防止条例によって規制されていた盗撮行為について、より罰則を強化して取り締まりを充実させるために制定されました。
これまでは、盗撮場所が分からなかった場合には条例は各都道府県によって違うため、処罰ができないことがありました。
また、各都道府県によって条例の内容が違うため、条例では処罰できなかったり、軽い刑罰しか定められていなかったりといった問題がありました。
法律になったことで、どこで行った盗撮でも罪に問うことが可能となり、刑罰も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金というより重いものとなりました。
さらに、本件のように、未遂罪についても処罰することができるようになりました。
なぜ不起訴となったのか
今回の事件では、Aは自分の行為を認めています。
そのため、通常であれば罰金などの刑罰を受けることになると考えられます。
しかし、今回は不起訴となっています。
不起訴となる場合にもたくさんの場合がありますが、今回の事件では、①嫌疑不十分、②起訴猶予のいずれかによって不起訴となっていると考えられます。
①嫌疑不十分とは、犯罪を証明するための証拠が少なく、間違いなくAが性的姿態等撮影未遂にあたる行為を行ったという証明ができなかったという場合です。
しかし、今回の事件では、Aは自らの行為を認めていますし、逮捕されていることから盗撮しようとしたという証拠は十分にあったと考えられるため、①嫌疑不十分のために不起訴になった可能性は低いと考えられます。
起訴猶予とは
②起訴猶予とは、犯罪の証明はできるが、いろいろな事情から判断して起訴をいったん見送ったというものです。
色々な事情としては、成立する罪の軽重、事件内容の軽重、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、被疑者の反省、社会的影響の軽重など様々な事情が考慮されます。
今回は盗撮事件ですので、被害弁償の有無や被害者の処罰感情、被疑者の反省などが考慮されたと考えられます。
つまり、おそらくAは被害者である女子中学生(未成年者なのでその両親)との間で示談を締結していると考えられ、また、警察官の職を失っていると考えられることから不起訴となったと思われます。
公務員によって被害を受けた場合
本件のように公務員から被害を受けた場合、加害者である公務員側から示談交渉を持ち掛けられることが多くあります(示談については、こちらのページもご覧くださいhttps://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/)。
なぜなら、国家公務員であれ地方公務員であれ、犯罪を起こして起訴されてしまうと、たとえ執行猶予がついたとしても失職してしまうからです。
また、警察官や消防士、教職員などについては、一般の公務員よりも懲戒処分の指針が厳しく定められており、司法判断つまり刑事処分の如何によって懲戒処分の重さが決まることになっていることが多くあります。
そのため、加害者が公務員の場合には、不起訴や略式罰金の処分を勝ち取るために示談交渉を持ち掛けてくるのです。
示談を受ける場合のメリットは、賠償を早期に受けることができ、接触しないなどの条件を付けることができることが挙げられます。
一方デメリットとしては、示談を受けることにより加害者の刑事処罰が軽くなったり、不起訴となって刑事処罰を受けることがなくなったりすることが挙げられます。
その他、事案によって示談を受けるメリットデメリットがありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
不同意性交等罪での示談について
犯罪被害に遭って警察に通報し、警察が事件として扱ってくれることになりました。警察に通報したところでは犯人が誰なのか分かりませんでしたが、警察の懸命な捜査の結果犯人が分かり、犯人が検挙されました。犯人は逮捕されているようなので、犯人が直接被害者とやり取りすることはできないようですが、逮捕されて間もなく、検察庁から電話があって、犯人の弁護士にだけ被害者の連絡先を教えてよいかと質問されました。
今回は、加害者側の弁護士から連絡先を教えてほしい、などと言われたときの対応と、結果の見通しについてお話しします。

1 参考事件
愛知県名古屋市北区に住む女性Aさんは、事件当時高校生でした。
ある日、部活動が遅くなって、夜に最寄駅から自宅までの道を歩いている最中、加害者の男からいきなり襲われ、人目につかないところまで引っ張られて、殴る蹴るなどの暴行のほか、男性器を女性器に挿入されそうになる、その様子を携帯電話端末で撮影されるなどの被害に遭いました。Aさんは、加害者との面識は一切ありませんでした。
Aさんが自宅に帰宅して夕食を食べるものの、このような経緯から制服が非常に汚れていたこと、夕食時の様子がおかしかったことなどから、Aさんの母親Bさんが、Aさんに何があったのか尋ねると、Aさんは先ほどのような経緯を話しました。これは大変だと思ったAさんとBさんは、事件当時来ていた制服などを持ってすぐに最寄りの警察署に向かいました。
その後、Aさんは深夜まで及ぶ取調べを受け、身体からも犯人のDNAを採取するために検体の保存が行われました。数日後にもまた数時間にも及ぶ取調べを受けました。防犯カメラ映像や、DNA型の文政期が上手くいったことから、先ほどの加害者が逮捕されました。
逮捕後すぐに、検察官から「加害者側が被害弁償をしたいということなので、加害者の弁護士だけにBさんの電話番号を教えても良いか」と言う電話が来ました。(この参考事件はフィクションです。)
2 法律解説
本件の加害者の行為については、不同意性交等罪にあたることはほとんど争いないでしょう。
また、不同意性交等の様子を撮影しているので、性的姿態等撮影罪も成立します。今回は、加害者弁護士から接触の試みがあったときの対処を開設するのがメインなので、詳しい条文解説は省略します。不同意性交等罪の解説は、こちらの記事もご参照ください。https://keiji-bengosi.com/gokan_kyoseiwaisetsu/
本件の加害者の行為については、示談や弁償等が無ければ相当厳しい処分になるのは間違いなさそうです。加害者や、加害者の弁護士としても、何とか示談や弁償をしたいという気持ちが高まっていると思われます。
3 対処法・弁護士によるサポート
まず考えなければならないのは、そもそも加害者の弁護士に電話番号を教えるかどうかです。基本的に、弁護士には守秘義務があるため、加害者本人やその家族に被害者の電話番号を教えることはないと考えられます。守秘義務違反には弁護士業務停止を含む相当重い懲戒処分が予定されるので、弁護士から加害者に被害者のプライバシー情報が漏れることはないのですが、どうしても心配ということであれば電話番号を教えないようにするとか、代理人の弁護士を依頼してその弁護士の連絡先を伝えてもらうということが考えられます。
次に考えるべきことは、示談金額及び誓約条項です。示談金額については、法律で金額が決まっているわけではないので、弁護士や加害者によって提示額も様々となり、妥当な金額であるのかどうか判断が難しい可能性があります。弁護士に依頼することによって、より打倒で納得できる金額になるように交渉することができる可能性がありますし、依頼をしないにしても、妥当な金額かどうかの回答をすることはできます。また、その他示談条件についても、一定の場所を一切通らない、一定の場所に近付かない等の内容が考えられます。このような条件も、弁護士や加害者によって提示内容は様々ですし、加害者側も被害者側の事情をよく知っていることは考えにくいので、最初から被害者側が納得できるような条件が提示されるとは限りません。やはり、その他示談の条件についても、弁護士に相談・依頼をすることで納得できる妥当な内容に近付く可能性が高くなります。
最も重要なのが、被害者の刑事処分を望まないような内容を示談書に記載するかどうかです。
被害者の刑事処分を望まないような内容の条項を、一般的には宥恕(ゆうじょ)条項と呼んでいます。宥恕というのは、要するに加害者を「許す」という内容であると理解していただいて構いません。
この宥恕条項については、加害者の刑事処分を軽減するのに相当重要な意味合いを持っており、加害者側としてはできるだけ示談書に盛り込みたい条項になります。示談書に記入した以上、基本的には「やっぱり許したくない」といったようなことを後から言うことはできなくなりますので、このような条項を入れるのであればよく気持ちを整理してから入れる必要性があると言えます。また、宥恕条項を入れるのであれば、その他の条件について妥当かどうかを判断し、妥当な条件に近付けるために弁護士が果たす役割も無視できないと言えます。示談についてはこちらの別記事もご覧ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
4 最後に
以上、加害者側の弁護士から接触の試みがあったときの対処法を簡単に紹介させて頂きました。
以上でご紹介させて頂いた他にも、各条項については示談・契約でしか使わないような専門的な用語が入っていたり、個別の事件事情により必要な条項が入っていたりいなかったりすることがあります。
加害者側としては、刑事処分を軽減するために被害者側に有利な条件を受け入れてくれる可能性も比較的高いのかもしれませんが、示談書全体の効力はよく検討しないといけませんし、細かい交渉を行うのは被害者側には大変かも知れません。
いずれにしても、弁護士に一度相談をしてみるのが示談交渉において正しい判断をしていくのに役に立つことでしょう。
刑事裁判における犯罪被害者の保護
犯罪被害者は、公開の法廷で加害者や傍聴人の目にさらされることに恐怖を覚えます。
そのため、被害者が証人として出廷することが難しくなり、検察官が起訴を断念せざるを得ないこともあります。
もっとも,法はそのような事態に備えて、法廷で犯罪被害者が加害者や傍聴人の視線から守られるために、各種制度を設けています。

<遮蔽>
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができます。証人尋問や遮蔽以外の被害者保護の措置については、法務省のホームページでも紹介されています。https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-4.html
具体的には、被告人と証人の間に衝立を設けることになります。
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いたうえで判断されることになります。
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができます。
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができます。
この場合も、傍聴人と証人の間に衝立を立てることになります。
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いたうえで判断されることになります。
上記の2つを併用し、証人が被告人にも傍聴人にも見られないように衝立が設置されることが多いです。
後に述べるビデオリンク方式による証人尋問においても、証人の映像が被告人や傍聴人から見られないようにできます。
この制度は、被害者等の意見の陳述や被害者参加人にも準用され、利用することが可能となっております。意見陳述や被害者参加については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/keijisaiban_sanka/#3%E3%80%80%E5%BF%83%E6%83%85%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E9%99%B3%E8%BF%B0
<ビデオリンク方式>
裁判所は、対象となる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であって、同一構内にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができます。
同じ裁判所内でライブ映像で会話をしながら尋問することになります。
対象は、
・不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、不同意わいせつ等致死傷、十六歳未満の者に対する面会要求等、営利目的等略取及び誘拐・人身売買(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る)、被略取者引渡し等、強盗・不同意性交等及び同致死の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
・児童福祉法違反、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律違反の一部犯罪の被害者
・そのほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
となります。
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いたうえで判断されます。
裁判所は、証人を尋問する場合において、相当と認めるときは、同一構内以外にある場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができます。
同じ裁判所内でない場所からライブ映像で会話をしながら尋問することになります。
対象は、以下の場合となります。
・犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。
・同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
・同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
・証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いたうえで判断されることになります。
これらの方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であって、証人の同意があるときは、その証人の尋問及び供述並びにその状況を映像及び音声を同時に記録することができる記録媒体に記録することができます。
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いたうえで判断されます。
性的な画像が拡散されてしまったら
性的な行為の相手方が性的な行為の様子を撮影して、その映像がその相手方の携帯電話端末などに残っている、という状況は想像するだけでもなかなか危険な状態であり、特別な状況でもない限りそういった撮影行為は許さないのが通常です。しかし、性的な行為の相手方を信頼している等の状況によって、自分が性的な行為をしている状況の映像を相手方に撮影させてしまい、その相手方から映像が拡散してしまうと言ったことは絶対にないことではありません。
今回は、性行為をしている姿の撮影に応じてしまい、その映像が拡散してしまったケースについて解説します。

1 参考事件
愛知県豊橋市内に住む25歳の女性Aさんは、交際している男性Bと性行為を行った際、Bから頼まれたこともあって、性行為をしている最中の様子をBが動画撮影するのを許してしまっていました。Aさんは動画が拡散するのは恥ずかしいと思っていたこともあり、Bには映像の拡散だけは絶対にしないようにお願いし、映像の拡散はしないということを信じて撮影に応じていました。撮影された映像には、Aさんの顔もはっきりと映っていました。
しかし、あるとき、AさんとBの関係が悪くなり、AさんとBは別れることとなりました。別れたときに、Bの方から付き合っているときに撮影した動画や画像をばらまく、と言うようなことは言われていませんでした。
別れてしばらくした後、AさんとBの共通の知り合いCから、Aさんの性行為の様子を撮影した動画を全く別のDから受け取ったことを知らされました。Aさんは、性行為の様子を撮影することは一応許していたものの、拡散までは許していなかったので、警察に相談することにしました。
警察署では、警察官が親身になって話を聞いてくれ、いわゆるリベンジポルノの事件として捜査してくれることになりました。
捜査の結果、BからDにAさんの性行為映像が送られたのち、DからCに送られ、なんとCも3人にその映像を送っていることが判明しました。自分の性行為映像が拡散していることを教えてくれたCさんまでもがその映像の拡散に加担していたことが分かり、Aさんは誰を信じたらよいのか分からなくなりました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 法律解説
本件のB、Cの行為については、それぞれ私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反に該当します。
法律の内容は以下です。リベンジポルノについては、こちらの記事もご参照ください。https://chiba-keijibengosi.com/revenge_porn/
(私事性的画像記録提供等)
第三条
1 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この法律では、撮影が無許可であることや、そもそも撮影者が自分であること等は一切規定されていませんので、少なくともBの行為もCの行為も指示性的画像記録提供等の罪に当たる可能性が高いと言えます。そのため、刑事処分もBとCそれぞれが受けることになる可能性が高いです。金銭的な損害賠償請求についても、BとCそれぞれに行うことができる可能性が高いです。
3 対処法・弁護士のサポート
本件では既に警察が捜査に動いている状態なので、警察の取調べ対応ももちろん重要ですが、最も重要なのは損害賠償や示談交渉の対応になります。本件は、Aさんの告訴が無ければ起訴が出来ない所謂「親告罪」にあたりますので、BやCからすれば少なくとも一応損害賠償や示談をすることを考える可能性が高いと言えます。
示談交渉や損害賠償請求に応じる場合は、BやCの捜査での認否や、弁解の状況について必ず確認した方が良いでしょう。認否や弁解の状況によっては、気持ちの面で示談をしたことについて後悔をする可能性も高くなりますし、不合理な否認や弁解をしている人との間で低額な示談金で示談をするのは非常に納得がいかないことと思います。
基本的に、示談や損害賠償の申し出は相手方の弁護人を通じて行われるので、上記のようなポイントを一応押さえていれば、ある程度納得のいく解決が得られる可能性が高いとも言えます。
しかしながら、相手は法律や交渉のプロであり、全く何も知識や技術の無い状態だと本当に納得のいく解決は難しいかも知れませんし、相手方の弁護士が刑事事件や被害者弁護の経験があまりない場合だと、法的に問題のある示談内容となる可能性もゼロではありません。
やはり、スムーズに、かつ納得のいく解決に近付くには、被害者弁護・刑事弁護のノウハウを持っている弁護士に相談してみるのが良いでしょう。示談交渉の流れなどは、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
4 最後に
以上、性的な画像が拡散してしまった時の対応について簡単に紹介させて頂きました。
もちろん、特に弁護士に依頼をすることなく解決をすることができれば、弁護士費用の持ち出しを気にする必要は無いのですが、納得のいく解決が出来なくなったり、相手方から弁償の申し出がない場合に損害賠償請求を行っていくのは困難になってきます。被害者弁護・刑事弁護のノウハウを持った弁護士がいれば、納得のいく解決にぐっと近づくことでしょう。
性的な画像を拡散されてお悩みの方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
【事件解説】高校生失明、警察官を業務上過失傷害で起訴
沖縄県で起きた警察官が高校生を失明させてしまい業務上過失傷害罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】
沖縄県警の巡査Aが、沖縄市内の路上で、男子高校生Vが運転するバイクを止めようと、警棒を持った右手を差し出して警棒を高校生の右目付近に差し出して警棒を高校生の右目付近にぶつけ、右眼球破裂や顔面骨折などの大けがを負わせた。
【報道の概要】
報道によると、警察は巡査Aについて、「特別公務員暴行陵虐致傷」の容疑で那覇地方検察庁に書類送検していたが、検察庁は「故意」を十分に立証できないと判断して「業務上過失傷害」に罪名を変更して起訴したということです。
現場に防犯カメラはなく、目撃者もいませんでしたが、警察は専門家への聴き取りや実験などで一連の行為に故意があると結論付けていました。
しかし、那覇地検は故意が十分に立証できなかったとして「注意義務を怠り、警棒を目の前に差し出すなどしたことを過失と捉えた」としているようです。
被害者のVやその家族は、「バイクを走行させていたところに、物陰から突然飛び出してきた警察官に警棒で殴られたと認識している。怪我も重傷で、相当強い力で殴られたことは明らか。たまたま手に持っていた警棒が過失によって当たったとは考えられず、公判請求の罪名には納得できない。」とコメントしている。
(朝日新聞DIGITAL2023年6月29日の記事https://www.asahi.com/articles/ASR6Y6RCVR6YUTIL019.htmlより抜粋)
【判決の概要】
本事件については、令和5年12月25日に那覇地裁で判決が出ています(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/092645_hanrei.pdf)。
判決ではAに対して罰金100万円が科されています。なお、検察官の求刑も罰金100万円でした。
判決文によれば、Aは夜間職務質問時において必要とされている機材を適切に用いることなく、バイクで進行してくるVに「おい、止まれ」と声を発しただけで進路上に入り、漫然と警棒を持った右手をVの方に差し出したという行為が、重大な傷害結果を発生させる危険性が高い行為であり、警察官の基本的な注意義務にも反するものといえるため、Aは強く非難されるとし、傷害結果も右目失明など重大であると認定しています。
しかし、Vの方も、進路前方にいるAを、自身に対する職務質問を行うため停止を求めている警察官と認識し、停止又は徐行するなどの衝突回避等の措置をとれた可能性は否定できないとして、Aの過失だけが本件の重大な結果を生じさせたものとは言えないとして、懲役刑ではなく罰金刑にすることも許される事案と述べています。
その上で、AがVに対して謝罪の言葉を述べ、損害賠償金として100万円を供託するなど反省の態度を示していることも考慮し、業務上過失傷害の罰金上限である100万円に処するのが相当と判断したとしています。
【解説】
①特別公務員暴行陵虐致傷(刑法196条)
本件で警察が書類送検した「特別公務員暴行陵虐致傷」は、警察官が捜査対象者に暴行などを加えて怪我をさせたときに成立する罪で、15年以下の懲役刑に処されることになります。
この罪が成立するためには、捜査対象者に暴行を加えようとする意思、つまり暴行の故意が警察官にあることが必要となります。
今回の事件で検察庁は、Aが意図的にVに当てようと思って警棒を突き出したということが証明できないと判断して、「特別公務員暴行陵虐致傷」の故意が立証できないとしているといえます。
もっとも、V側がコメントしているような事情があれば、「特別公務員暴行陵虐致傷」の故意が認められると考えられますが、今回は防犯カメラや目撃者など客観的に故意を立証できる証拠がなかったために、検察庁は争われてしまうと負けてしまうと考えて罪名を変更したと考えられます。
②業務上過失傷害(刑法211条)
本件で起訴された「業務上過失傷害」は、業務上必要な注意を怠った過失によって人に傷害を負わせてしまった時に成立する罪で、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
「特別公務員暴行陵虐致傷」と比べて懲役刑の上限がかなり下がり、さらに罰金刑もある点で大きな違いがあります。
これは、故意による犯罪か、過失による犯罪かという点、つまりあえて行ったのか不注意でやってしまったのかという点による違いといえます。
今回の判決では、懲役刑ではなく、罰金刑の上限額である100万円の罰金刑が科されています。
③刑事裁判と民事裁判
今回の事件では、刑事裁判でAは有罪となり、罰金刑を受けています。
しかし、罰金は国に対して支払われるため、Vに対してはこの裁判によって金銭が支払われることはありません。
Vが治療費や失明してしまったことの慰謝料など、金銭的な賠償を受けたいと思う場合には、別途民事裁判を起こす必要があります。
民事裁判では刑事裁判と違って、訴える側(原告)が被害が発生した原因や被害の内容、損害賠償の額などを証明する必要があり、時間も労力もかかってしまいます。
そのため、多くの場合には示談や和解といった任意交渉で賠償を求めていくことが多くなります。示談についてはこちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
【公務員によって被害を受けた場合には】
公務員から被害を受けた場合には、懲役刑や禁錮刑の判決が下されるとたとえ執行猶予がついたとしても公務員としての身分を失ってしまうため、処罰を軽くするために示談交渉の打診があることが多いと思います。
示談を受けるべきか否かや、示談を受けた場合に公務員に下される処分がどうなるか、報道されるのかどうかなど、様々な疑問や不安が生じてくることと思いますので、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスをもらうことで、自分の希望を叶えるにはどうすればよいのか明確になりますし、弁護士に依頼すれば窓口になって交渉してくれるので精神的にも安心することができます。
不同意わいせつ被害に遭った時の弁護士の選び方
犯罪被害に遭ったとき、加害者側から任意の謝罪・弁償が受けられれば、犯罪の種類や被害の内容にはよりますが、それだけでも納得のいく解決に繋がるかも知れません。任意の謝罪・弁償が受けられなくても、警察・検察が動いてくれることにより、結果として謝罪・弁償、あるいは示談をすることも出来るかも知れません。しかし、加害者側から任意の謝罪・弁償が無く、自分だけで警察に行っても事件を立件してくれるか不安であったり、加害者側から示談の提案はあったがどうしたらよいか分からないこともあると思います。
そのような時に弁護士に相談・依頼することが検討されるのですが、どういった観点から弁護士を選ぶと良いのでしょうか?以下、簡単な参考事例を基にご説明いたします。

1 参考事件
愛知県内に住むAとBの夫婦には、高校3年生で18歳の娘Cがいました。
ある日、Cが両親ABの知らないところでSNSを通じて知り合った24歳の社会人Xから性的暴行を受けるという不同意わいせつの被害に遭いました。
A、B、Cで警察署に相談に行ったところ、どこの誰なのかわからないし自分で近付いて行ったのだから事件にできない、と言うような対応をされました。A、Bはこの対応について不審感を持ちましたが、どう対応すれば良いか分からずにいました。インターネットで「犯罪 被害 弁護士」と探す等していたところ、膨大な数の法律事務所のホームページが出てきました。A、Bの夫婦は今度はどうやって弁護士を選んだらよいのかわからず、まずは検索ページの一番上に出てきた法律事務所に電話をしたところ、その事務所からは「犯罪の被害者案件は扱っていない」と回答されました。A、B夫婦はますますどうしたらよいか分からなくなりました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 法律解説
(不同意わいせつ)
刑法第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
以下略
本件に関しましては、性的行為をするつもりのない被害者Cが加害者Xの家に行ったところ、加害者Xがむりやり被害者Cを押さえつけて胸を触った事件等を想定していただければ問題ありません。不同意わいせつ罪についての解説は、こちらの記事もご参照ください。https://keiji-bengosi.com/gokan_kyoseiwaisetsu/
3 弁護士の選び方
弁護士の選び方としては、料金、取扱分野、実際に接したときの相性といったところがあるでしょう。その他の記事では書ききれないような情報をひとまず考慮せずに決めるのであれば、この3つのなるべく多くクリアしている弁護士に相談・依頼するのがよいことになります。弁護士に依頼する経路を切り口として説明していきます。
(1) 知り合いの弁護士に依頼する
この方法が、基本的には上記の3つの要素をクリアしやすいと思われます。弁護士との関係性から、無理な料金設定をされることは少ないですし、事件当時まで知り合いなので相性の問題もクリアしていると考えて良いはずです。何より、弁護士の人間性などをよく知っていることが最大の安心材料になるでしょう。
問題としては、やはり取扱分野の点になります。一定の関係性があるので依頼も受けてもらいやすく、誠実に事件処理をしてくれるのは間違いなさそうですが、普段扱っていない分野の仕事をすれば誰しも大なり小なりのミスをする危険性が高まります。
しかし、最大の問題としては、そもそも知り合いの弁護士がいないことです。知り合いの弁護士がいなければ、知り合いの弁護士に依頼することは物理的に不可能です。
なお、先述の事例も、知り合いの弁護士がいない設定にしています。
(2) 弁護士会に相談する
弁護士とつながる方法として、インターネットのほかに地域の弁護士会に相談に行く方法もあります。弁護士会に行けば、「日弁連犯罪被害者法律援助制度」など、弁護士費用の援助を受けられる制度について説明を受けられるかもしれないので、料金面もクリアできる可能性が高くなります。
しかし、上記のような弁護士費用の援助制度に対応していない弁護士もまた多いと思われますし、基本的に弁護士費用の援助制度については利用にあたって資力制限があります。
(3) インターネットでの検索
インターネットで検索して弁護士を探す場合、相談・依頼する弁護士の候補自体は大量に出てきます。ポータルサイトなども使えば、より効率的に弁護士を探すことができるでしょう。
問題としては、それでも犯罪被害者の弁護を扱っている弁護士かどうかわからない可能性がある、という点です。しかし、この点については、電話等で取り扱いを確認すればまだ間違いは防げます。
料金面については、弁護士報酬は各法律事務所が自由に設定しているので、様々な料金体系があります。各事務所の説明を聞いた上で、依頼するかどうかを決めると良いでしょう。
最大の問題は、弁護士との相性の問題です。被害者弁護においては、どうしても警察署や検察庁とのやり取りも多く、事件が解決するまでに時間がかかる上、相談しなければならない事柄も多く出てきます。時間が無くなってしまうので、あまり多くの法律事務所を回るのも考え物ですが、明らかにおかしい感じがする弁護士には依頼などをしない方が良いでしょう。
4 最後に
弁護士の選び方や、弁護士とのつながりを得るための経路は様々ありますが、主なものをこの記事でご紹介させて頂きました。
犯罪被害に遭われた際は、まずは被害者弁護を扱う弁護士への相談を検討した方が、より納得できる解決に繋がります。
犯罪被害に遭われて、加害者を告訴したい、損害賠償を請求したいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。
ストーカー被害に遭ったら…
ストーカーの被害にあった場合において、被害者としてはどのような対応を必要とするのかなどについて、参考事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 参考事例
福岡県北九州市の飲食店で働いているXさんは、同僚であるAさんに交際を求められましたが、それを断り、その日からAさんと会話を避けるようになりました。
そうしたところ、Aさんが、Xさんへの思いを諦めることができず、Xさんの住所を、同僚から聞き出し、Xさんの自宅周辺をうろつくようになりました。
Xさんは、Aさんが自宅周辺をうろついているのを見かけ、不安に思い、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
2 Aさんの刑事責任について
AさんがXさんの自宅周辺をうろつくことは、Xさんに対する恋愛感情を充足する目的で、Xさんに対し、その住居等の付近をみだりにうろついたものといえ、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)2条1項柱書の「つきまとい等」に該当します。
そして、この「つきまとい等」が反復して行われた場合、「ストーカー行為」(同法2条4項)に該当することになります。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとされています(同法18条)。ストーカー規制法の解説については、こちらの記事もご参照ください。https://fukuoka-keijibengosi.com/stalker/
3 Xさんのとるべき行動とは
Xさんとしては、まず警察に相談することが考えられます。
ストーカー規制法では、警察本部長等が、つきまとい等を行い、更に反復して行うおそれがある者に対し、更に反復して同様の行為を行わないよう警告することができます(同法4条1項)。
また、公安委員会が、場合によっては、公安委員会が禁止命令を出すということも考えられます(同法5条1項)。
この禁止命令に違反し、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処するとされています(同法19条1項)。
Xさんにとっては、身の安全や生活の平穏が最優先事項です。
そこで、警察や公安委員会による手続によって、今後、ストーカー行為がされないようにしていく必要があります。
もっとも、単に、口頭の被害申告をするだけで警察が動いてくれる可能性は低いと思われます。
特に、自宅周辺をうろつかれるなど、ストーカー行為の内容によっては、証拠が残りにくいものがあります(たとえば、執拗に電話を掛けてくる場合には、通話記録が残るため、比較的証拠が残りやすいといえます。)。
そこで、どのような証拠を収集、保全しておく必要があるのか、弁護士のアドバイスが必要になってきます。
特に、ストーカー事案の場合、被害者自身に、身の危険が生ずる可能性もあるので、証拠収集も慎重に対応する必要性が高いといえます。
Xさんとしては、そうして収集した証拠とともに、警察に被害申告をすることが考えられます。
4 被害申告後のこと
ストーカー事案における被害者は、警察に被害申告をして終わりというわけにはいきません。
警察から事情聴取を受けることもありますし、加害者側から示談をして欲しいと連絡があることも考えられます。
しかし、ストーカー事案における被害者にとっては、加害者側とやり取りをするだけで、大変大きな精神的負担になりますし、さらなるトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
示談においても、単に示談金を受け取ることによって安心した生活を送れるとは限らず、示談の中で、接触禁止や口外禁止などを約束してもらうということも重要になってきます。
少しでも安心した生活を送れるために、どのような内容の示談をした方がいいのか、弁護士からアドバイスをもらう必要がありますし、加害者側とのやり取りを弁護士に任せることも重要といえます。示談対応については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー被害に遭われた方への様々な支援を行っています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
特殊詐欺被害~複数人からの示談の申入れ~
オレオレ詐欺などの特殊詐欺被害に遭ったときに、複数人から示談の申入れがある場合があります。その場合の問題について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
東京都葛飾区に住むAさんは、特殊詐欺の被害に遭い300万円をだまし取られてしまいましたが、警察の捜査の結果、Aさんを騙した掛け子役のXと出し子役のY及び指示役のZの3人が逮捕されました。
その後、XとYのそれぞれの弁護人から別々に、Aさんに対して「300万円の賠償と引き換えにXに対して刑事処罰を求めないという示談をしてくれないか」という連絡がありました。
Aさんは、XやYとの示談をした場合に自分が不利にならないために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けることにしました。
(フィクションです)
示談とは
示談と一口に言っても、その内容は様々です。
単に賠償金(被害弁償金・示談金・解決金)を受け取っただけでも示談と言われることがありますが、基本的には、賠償金を受け取ったうえで、それ以上にお互い金銭のやり取りはしないという条項(「清算条項」という。「本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」というような文言のことが多い。)を設けて解決を図ることを示談や和解ということが多いです。
もっとも、刑事事件においては、さらに「加害者に対して刑事処罰を求めない」などの加害者を許す条項(「宥恕条項」という。)まで設けた示談(刑事示談)を行うことが多いです。
示談については、こちらもご覧ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
複数人から示談の打診があった場合~被害金額を超えて示談金を受け取れるか~
刑事事件の内容によっては、加害者が複数人いる場合があり、そういった場合には、複数人から示談を申し込まれることもあります。
損害賠償請求をする場合には、加害者が複数人いるときには、共同不法行為となり、被害者の方は加害者それぞれに対して自分が被った損害の額全額を請求することができます。
事例のAさんの場合には、Xに対して300万円、Yに対して300万円、Zに対して300万円をそれぞれ請求することができます。
しかし、仮にXがAさんに対して300万円を支払った場合には、AさんはさらにYやZに対して300万円を請求することは出来なくなります。
もっとも、示談交渉の中で受け取る場合には、あくまでも任意交渉ですので、一人から被害金額全額を受け取ったとしても、別の人から別途解決金として金銭を受け取るということは可能です。
そのため、事例のAさんの場合には、XとYそれぞれから300万円を支払うという打診が来ていますので、それぞれから300万円を受け取ることが可能です。
複数人から示談の打診があった場合~宥恕の効果~
共犯事件で、加害者全員から示談の申入れがあった場合、示談を受けると当然加害者全員に対して効果を与えることになります。
特に宥恕文言が入っている示談を締結した場合、加害者全員が不起訴処分となり刑罰を受けなくなる可能性があります。
もし、どうしても刑罰を受けてほしいと考えている場合には、賠償金は受け取るが許すつもりはないということを明確にしておくべきでしょう。
問題となるのは、共犯者の一部の者からしか示談の申入れがなかった場合です。
共犯者の一部とだけ示談をしたとしても、その効果は示談をしていない共犯者に対しても及ぶ可能性があります。
たとえば、事例のAさんがXとYから示談金の支払を受け、XとYには刑罰を求めないという宥恕付きの示談をした場合、XとYの処分について軽くなることは当然ですが、示談金を受け取ったことにより、Zについても有利な事情として扱われ、Zの処分も軽くなる可能性があります。
特に、告訴をしている事件について、共犯者の一部とだけ示談して、示談の内容としてその一部の共犯者に対する告訴を取り消すという文言が入っていた場合、告訴の取消しは共犯者全員に効力が及ぶため(刑事訴訟法238条1項)、共犯者全員に対する告訴の効果が失われてしまいます。
刑事裁判にかけるために告訴が必要とされている事件(親告罪)の場合には、一部の者に対する告訴の取消しであったとしても、全員に対する取消とされてしまうので、刑罰を与えることが出来なくなってしまうことに注意が必要です。
その他、示談における一般的なメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/toraburunaiyou/keiji_tetsuzuki/jidan/faq1.html
示談の申入れがあれば
示談の申入れがあった場合、その申入れの内容が法律的に見て妥当かどうかは経験を積んだ弁護士に確認してもらうのが一番です。
特に複数人から示談の打診があった場合には、安易に示談を受け入れてしまうと思ってもいなかった効果が発生する場合もあります。
そのため、示談の申入れがあったときにすぐに結論を出すのではなく、専門家である刑事事件専門の弁護士にまずは相談してみてください。
少年事件への被害者としての関わり
少年事件による犯罪被害に遭ってしまった場合、手続の中で被害者ができることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。少年事件においては、適用される少年法の趣旨や理念のもと、加害者である少年を保護するという側面が重視され、被害者の置かれる立場がより厳しくなりがちです。
被害者の立場でどのような対応が取れるかお悩みの場合は、被害者支援に詳しい弁護士へ相談しましょう。

被害者等による記録の閲覧・謄写
家庭裁判所は、少年に係る保護事件について、審判開始の決定があった後、当該保護事件の被害者等又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとされております。
閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合は除かれます。
申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければなりません。
・申出人の氏名、名称又は商号及び住所
・閲覧又は謄写を求める記録を特定するに足りる事項
・申出人が申出をすることができる者であることの基礎となるべき事実
・閲覧又は謄写を求める理由
この申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後3年を経過したときは、することができません。
記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはなりません。
加害少年の名前をもとに事件を特定して手続が進められますので、分からない場合は被害者が警察署で加害者の名前を教えてもらうことになります。
被害者等の申出による意見の聴取
家庭裁判所は、少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させることとなります。
ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、実施されません。
申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければなりません。
・申出人の氏名、名称又は商号及び住所
・当該申出に係る事件を特定するに足りる事項
・申出人が申出をすることができる者であることの基礎となるべき事実
意見を聴取するときは、申出人の心身の状態に配慮して実施されます。加害少年の前で意見を述べたいと希望した場合でも、家庭裁判所が認めないこともあります。
被害者等による少年審判の傍聴
少年審判は非公開が原則です。
家庭裁判所は、被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができます。
対象事件は、以下の事件となります。
・故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
・業務上過失致死傷等の罪
・過失運転致死傷等の罪
いずれも被害者を傷害した場合にあっては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限ります。
家庭裁判所は、少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たっては、少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければなりません。
家庭裁判所は、審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができます。
裁判長は、審判を傍聴する者及びこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たっては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければなりません。
傍聴・付添いをした者は、正当な理由がないのに傍聴により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、傍聴により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはなりません。
家庭裁判所は、審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければなりません。裁判長は、適正な審判をするため必要があると認めるときは、少年以外の者を退席させる等相当の措置をとることができます。少年審判の流れについては、こちらの記事もご参照ください。https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/
被害者等に対する説明
家庭裁判所は、少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明することになります。申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後3年を経過したときは、することができません。
説明を受けた者は、正当な理由がないのに説明により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、説明により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはなりません。
被害者等に対する通知
家庭裁判所は、少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知することになります。少年事件における被害者への通知制度等については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/syounenjiken_higaisya/
・少年及びその法定代理人の氏名及び住居
・決定の年月日、主文及び理由の要旨
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、除外されます。申出は、終局決定が確定した後3年を経過したときは、することができません。
通知を受けた者は、正当な理由がないのに通知により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、通知により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはなりません。
加害者が不起訴処分になってしまったら
犯罪被害に遭っても、加害者が不起訴処分となって処罰されないこともあります。不起訴処分とはどのようなものか、加害者が不起訴処分となった場合に被害者としてできることはあるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

不起訴処分とは
犯人・加害者を刑事裁判にかけるか、すなわち起訴の判断は、検察官が行うことになります。しかし、全ての犯罪が起訴されるわけではありません。
まず、きちんとした証拠が不十分だと判断されたら、嫌疑不十分で起訴されないことがあります。また、犯罪行為が認められ、きちんとした証拠があっても、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断したときは、起訴猶予で起訴しないことができます。不起訴処分については、こちらの記事もご参照ください。https://sapporo-keijibengosi.com/fukiso/
検察官は、公訴を提起しない処分をした場合において、被害者等の請求があるときは、その理由を告げることになります。
しかし、実際には、「起訴猶予」「嫌疑不十分」等だけ伝えられ、詳細な理由の開示はなされないことがほとんどです。
検察審査会への不服申し立て
被害者等は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができます。審査申し立ての流れについては、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/kensatukan_syobun_fufuku/
検察審査会は、地方裁判所及び地方裁判所支部にあります。審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければなりません。審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができます。
検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員で組織されます。検察審査会議は、非公開で審理されます。
起訴を相当と認める起訴相当決議、公訴を提起しない処分を不当と認める不起訴不当決議、公訴を提起しない処分を相当と認める不起訴相当決議、のどれかが判断されることになります。
検察審査会議の不起訴相当・不起訴不当の判断は、過半数でこれを決することになります。起訴相当の議決は、検察審査員8人以上の多数によらなければなりません。
検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければなりません。
起訴相当の議決にもかかわらず、検察官が公訴を提起しない処分をした場合は、検察審査会は当該処分の当否の審査を行わなければなりません。
その結果、検察審査会が検察審査員8人以上の多数によって起訴相当の議決をしたら、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければなりません。
指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行うことになります。検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをすることになります。
早めに弁護士に相談を
しかし、被害者が不起訴処分に不満を持っても、検察官がいったん不起訴処分をしてしまったら、そこから起訴になることはほとんどありません。検察審査会を通じて起訴がなされることもほとんどありません。被害者は、起訴されることを期待して何もしないでいると、状況がどんどん悪化してしまうことがあります。
犯罪被害に遭ってしまった場合は、ぜひ早めに弁護士に相談して、今後の対応を検討するようにしてください。
出来るだけ起訴されるためにはどのような対応が必要か、不起訴の可能性が高いのであればどのように対応すればいいのか、などを検討していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、犯罪被害者支援の弁護活動に精通した弁護士が所属しております。ご自身やご家族が犯罪の被害者となってしまったら、早めにご相談してください。
対応が遅れると、加害者側のペースに乗ってしまい、最終的に被害者側の納得できない形で終わってしまう可能性があります。
まずはお気軽にお電話して無料相談を受けていただけたらと思います。03-5989-0892までお電話してください。丁寧にご説明させていただきます。