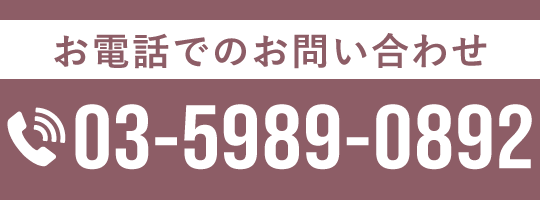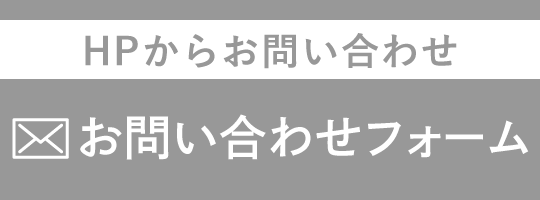Archive for the ‘犯罪被害者支援’ Category
子供が怪我をさせられた場合に親としてどう動くべきか

子供が怪我をして帰ってきたときに、親としてどういった動きをするべきなのか、様々なパターンに応じての対応を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
中学生のA君が、顔に大きな痣を作って帰ってきました。
今朝学校に行く際には、そのような怪我がなかったため、お母さんはA君に話を聞くことにしました。
まずはしっかりと話を聞く
子供が怪我をして帰ってきたときには、まずしっかりと話を聞いてあげましょう。
話を聞くときは、矢継ぎ早に質問するのではなく、「その怪我はどうしたの?」という最初の質問以外は、子どもが話をしてくれるのを待ちましょう。
あまりにも、親の方から質問をしてしまうと、子どもの記憶に影響してしまい、実際の事実とは異なる記憶に改ざんされてしまう可能性があります。
たとえば、「誰にやられたの?」と聞いてしまうと、自分で転倒してできた怪我だったとしても、誰かに殴られたと言ってしまうかもしれません。
また、誰かに殴られたりして怪我をしてしまっている場合には、なぜ殴られてしまったのかとても気になると思いますが、なんで殴られたのかについて根掘り葉掘り聞いてしまうと、自分のことを良く見せようとして相手のことだけを悪く言ってしまったり、逆に自分は全く悪くないのに、自分にも悪い部分があったのではないかと不安になり、きちんと事実を話せなくなってしまう可能性があります。
そのため、寄り添う姿勢をしっかりと見せつつ、気長に子供の話に耳を傾けるように気を付けましょう。
参考:https://www.nnvs.org/wp-content/themes/hanzaihigai/images/network/pdf/otonawbsaisyu.pdf
病院に連れて行く
ある程度話を聞いたら、病院に連れて行きましょう。
顔面の怪我の場合には、脳などにも影響があることがありますので、念のため脳神経外科なども受診するといいでしょう。
また、他にも怪我をしている部分がないかもよく観察しましょう。
もし、誰かに怪我をさせられたということであれば、診断書を医師に作成してもらいましょう。
学校内で怪我をしていた場合
学校内で怪我をしていた場合、誰かに怪我をさせられたということであれば、まずは学校に相談してみるのがよいでしょう。
一時的な喧嘩だったのか、いじめを受けているのかなどを学校に調査してもらいましょう。
そもそも、怪我をしていることを学校が把握していれば、学校の聴き取り調査が行われている可能性もありますので、学校に相談することにより、より詳細な状況が分かる可能性もあります。
しかし、学校によっては、きちんと調査してくれない場合があります。
そういった場合には、学校が公立校であれば、学校を管轄している市町村の教育委員会に相談することもできます。
特にいじめが疑われる場合には、教育委員会に相談することで第三者委員会が設置されるなど、より詳細な調査をしてもらえる可能性が出てきます。
一方、私立校の場合には、教育委員会の権限が及ばないため、原則として学校内で解決してもらうことになります。
そのため、私立校の場合には、学校に相談したにもかかわらず、加害者の子どもについても保護しようとして、きちんと調査が行われなかったり、お互いに悪い部分があったとして大事にはしないようにという圧力が学校側から加えられる事例も散見されます。
そのような場合には、弁護士に相談して、学校へ働きかけてもらうなどしていく必要が出てきます。
学校外で怪我をしていた場合
学校外で怪我をしていた場合、学校に通っている生徒から怪我をさせられたのか、全く関係のない人から怪我をさせられたのかによって対応が異なります。
まず、学校に通っている生徒から怪我をさせられた場合には、学校内で怪我をしていた場合と同様にまずは学校に相談しましょう。
全く関係のない人から怪我をさせられた場合には、すぐに付近の防犯カメラなどで犯人を特定する必要が出てくるため、近くの警察署に相談しましょう。(大阪府警察の場合https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/kodomo_jyosei/20578.html)
警察署に行く際に、診断書をすでに取得している場合には、診断書も一緒に提出して、被害届を出しましょう。
警察が被害届を受理してくれたら、捜査が開始されますので、捜査の結果などを知らせてもらえるように警察にお願いしておきましょう。
警察が捜査をするにあたっては、警察から子供に対して、どういった状況だったのかを詳しく聞かれたり、再現をさせられたりします。
子供が一人で対応することが不安という場合には、保護者の立会いを認めてもらったり、事前に弁護士と契約をして弁護士に付添や弁護士に対して子供がしゃべってくれた内容を弁護士がまとめた書面を警察に提出することができます。
犯人が特定されたら、基本的に犯人を特定したという連絡が警察から入ります。
民事事件と刑事事件
警察が犯人を特定した場合には、その犯人は刑罰を受けるか否かを決める手続に乗せられます。この手続を刑事事件手続といいます。
刑事事件手続に関しては、被害者としては捜査に必要とされる範囲で協力を求められますが、それ以外では基本的に蚊帳の外に置かれてしまいます。
犯人がどのような処分を受けることになったのかについては、「被害者通知制度」などを通じて知ることができます。
また、犯人の刑事裁判に参加して意見を述べたり犯人に質問したりすることも一部の事件では可能です(被害者参加制度)。
被害者参加制度を利用するにあたっては、弁護士に依頼して、弁護士が代わりに質問したり、意見を述べたりすることもできます。
このような犯人に刑罰を与えるか否かを決める手続とは別に、直接犯人に治療費や慰謝料など金銭を請求することもできます。
このことを損害賠償請求といい、民事事件と言われます。
民事事件の場合には、直接相手との話し合いを行う「任意交渉」と裁判を通じて強制的に犯人に金銭賠償を求める「民事裁判手続」に大別できます。
いずれにしても、犯人と対峙することになりますので、弁護士を代理人として選任して、弁護士に窓口となってもらって交渉等をしていきましょう。
このように刑事事件と民事事件は別の手続ですが、刑事事件の手続の中で犯人に対して損害賠償を請求することが出来る「損害賠償命令」の制度や刑事事件と民事事件の両方を話し合いで解決する「示談」という手続もあります。
分からないことがあれば弁護士に相談を
このように、子どもが怪我をして帰ってきた場合には、様々なことを考えないといけません。
子どもの話を聞いて、今後の対応をどうするかとても不安になることでしょう。
そういったときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、法律的な解決だけでなく、話し合いでの解決やご家族のためになる解決を一緒になって考えてくれます。
どのような対応が考えられるのか、それぞれの対応についてのメリットやデメリットなど弁護士に相談することで、今後どのような対応をとればいいのかについても明確になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
子供が被害者になったときに親として出来ること

自分の子供が犯罪の被害者になったときに、親としては、子供の被害について心配し、悲しみの気持ちや、激しい怒りの気持ちを覚えることになるかと思います。犯人を警察に捕まえてほしい、損害賠償金を支払わせたいなど、思うことは様々ですが、「何が出来るのか」、「何をすべきではないのか」と言ったことを理解していくことで、子供が犯罪の被害者になったときも冷静かつ的確に動くことが出来、結果的に親としての思いも実現できることになるでしょう。
今回は、子供が犯罪被害に遭ったときに親として出来ることは何か、逆にやってはいけないことは何かについて解説したいと思います。
1 親として出来ること 警察に被害を申告する。
まず真っ先に思い浮かぶのが、警察に通報する、被害届を出すなどして、警察に被害を申告することです。
可能な限りお子様を警察署に連れて行って、警察の方になるべく具体的に被害状況を説明できるようにしてください。
近年では、証拠が薄いとか、人員が足りないとか、警察沙汰にするほどのことでもないいうようなことを言って被害届を受け取らないような対応をする警察官は少なくなっていますが、それでも完全にゼロにはなっていないのが現状です。
何度も警察署に通う、お子様と話し合って言い分をまとめてみる、証拠となるようなものが無いかもう一度探してみる、といったことで、事件捜査が前に進んでいく可能性が高まります。
2 親として出来ること 被害弁償の請求をする
多くの犯罪行為は、民法上の不法行為にもあたり、被害があれば財産的損害や精神的損害等の賠償を請求できます。
加害者の住所や氏名に関しても、警察署、検察庁に教えてもらうようにお願いすれば、教えてもらえる可能性があります。元々加害者が顔見知りであるような場合は、警察の捜査や裁判などで明らかになった事実を基に、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起できます。
また、加害者の方から示談交渉を持ちかけられる場合もあります。納得のいく条件であれば示談をしてお金を支払ってもらっても良いと思います。
3 親として出来ること 精神的ダメージのケアを行う
自分の子供が犯罪の被害に遭った場合、やはり身体・財産のダメージだけでなく、精神的なダメージが出ることもあります。特に、未成年の子が被害に遭った等の場合、精神的ダメージは特に大きくなりますし、精神的ダメージの程度によっては被害に関する供述が出来ないような場合があります。
その場合、精神科の病院を探して通院させ、カウンセリング等を受けさせれば、精神的ダメージの緩和に繋がります。警察や検察の方に関しても被害者の心情には非常に配慮して取調べを行うことが多いです。また、筆者の経験上、事件の解決に向かって動いていくことが実感できると、精神的ダメージの回復に繋がっていくことがあります。
4 逆に、子供が被害にあったときに親としてやってはいけないこと
まず、親としてやってはいけないのは、無理に被害届を出そうとしたり、無理にお子様に被害事実を語らせようとすることです。既に被害に遭っているのに、自分の親に子のようなことをされては、二次被害となることがあります。あくまで、お子様の、処罰したいという気持ちがスタートであるべきです。
次にやってはいけないことは、加害者に対して直接会いに行って金銭を要求したり、殴り込みに行くようなことです。まっとうな金銭要求であれば特に犯罪にはなりませんが、恐喝との線引きは難しいです。殴り込みや暴行・傷害に関しては、やってはいけないことなのは常識なのですが、お子様が被害に遭ってしまえば、分かっていても犯罪にあたるような行為をやってしまうかもしれません。何より、警察に行く前に親だけで加害者のもとに直接向かうことで、警察が動くことを恐れて、加害者が逃げたり証拠隠滅をすることだってあります。基本的に、加害者のもとに自分だけで向かうメリットはありません。
5 では、弁護士がいると何が出来るか?
1に関しては、被害届を提出する場面に付き添う、被害状況に関して分かりやすくまとめる、法律的な問題点に関して検討をする、警察の方と話し合うということをすることによって、被害届を受理しやすくすることが出来ます。警察の方々も、弁護士が付添であれば態度が変わることが多い(残念なことでもありますが)ですし、弁護士に対してであれば被害届受理に向けて何が足りないかなどを話しやすいです。
2については一般の方でも比較的分かりやすいのですが、裁判や交渉に関しては当然弁護士に任せる方が、スムーズに進みます。訴訟や交渉そのものだけでなく、特に相手方が被害者の方と面識がない場合、被害者本人よりも被害者の依頼した弁護士のほうが、加害者の連絡先を教えてもらいやすいです(弁護士は守秘義務を負う職業のため)。示談を持ち掛けられている場合、妥当な条件であるのかどうかのアドバイスも出来ますし、代理人として交渉すれば、より良い条件での示談が出来ることもあります。
3に関しては、精神科クリニックに行ったほうがよいか、どこに行けばよいかアドバイスが出来るほか、弁護士から警察や検察に対して、被害者の心情にさらに寄り添った取調べをするように申し入れをすることも出来ます。筆者の申入れによって、未成年の被害者の取調べに母親が同席することが出来るようになったこともあります。
4に関しては、弁護士に依頼をいただければ、基本的に親御様が交渉によって責任を負うことは無くなりますし、それぞれの事案にあった解決が出来るようになります。色々な加害事例や被害事例を見ている弁護士に関しては、被害に遭った子供に対してどう接するのがよいのかも理解していることが多いです。基本的に弁護士であれば、証拠隠滅や逃亡などをされないようにすべき準備もよく理解してます。
6 子供が被害に会った時はぜひ弁護士にご相談ください
ここまで、子供が被害に会ったときに出来ることやすべきでないことを紹介しましたが、あくまで一般的な話に過ぎません。犯人との関係値や、事案の性質など、出来ること、やるべきでないことは様々になります。
一度弁護士にご相談いただければ、より有効なアドバイスが出来ます。
子供が被害に遭ってお困りの親御様は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
被害者参加と刑罰への影響

犯罪被害に遭われた方にとって、加害者の量刑がどうなるか、というのは非常に大きな関心事になるかと思います。特に、大きな怪我をした事件や、被害者の方が亡くなってしまったような事件で、罰金や執行猶予の判決になるようなことになると、被害者やご遺族の方からしたら納得がいかないと思います。
そこで、被害者側にとって何とかならないか、被害者参加によって加害者にできるだけ重い処分を与えることができないか、が気になるところだと思います。今回は、被害者参加によって量刑にどのような影響があるのか解説していきたいと思います。
1 参考事例
名古屋市内に住むAさんは、ある日、歩道を歩いていたときに、ハンドル操作を誤ったBの自動車が突っ込んできて衝突し、そのまま死亡しました。
Aさんの遺族であるCさんは、なんとかBに厳しい判決が下るようにできないか考えました。被害者参加制度などを使ったら果たしてそうなるのか、法律の専門家などではないので分かりませんでした。Cさんは、被害者参加制度などの利用を検討するため、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 法律上の問題点
上記事例について、過失運転致死罪に当たるのは間違いないでしょう。そのため、被害者参加の出来る事件に当たります。
また、Cさんは、とりあえずここでは被害者参加が出来る資格があるとします。そのため、被害者参加が出来ること自体には問題がありません。
しかし、被害者参加の効果を裁判上どのように考慮していくのかについては、以下のような規定があり、被害者参加人のした事実又は法律の適用についての意見陳述は証拠とはならないと定められております。
刑事訴訟法
第316条の38
第1項
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
略
第4項
第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
そのため、被害者の方が上記の意見陳述をしたとしても、裁判の結果については少なくと大きく変わることはない、というのが刑事訴訟法上の扱いであると言えます。
3 どのように弁護活動をしていくのか
それでは、被害者参加によって量刑を変えていこうと考えた場合、どのような活動をしていけば良いのでしょうか?
一つは、まず検察官に働きかけを行うことです。被害者参加における検察官の活動については、このような規定があります。
(一応、起訴までこぎつけたことを前提とします。)
刑事訴訟法
第316条の35
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。
この規定については、証拠調べの請求だけでなく、論告や求刑といった量刑に直結する訴訟活動についても意見を述べることができます。そして、意見を述べた場合、当該訴訟活動を行った理由を被害者参加人やその弁護士に説明することになります。
基本的に多くの検察官は、被害者の意向になるべく沿うように活動しようとしますので、量刑についても被害者の意向に沿ったものにしてくれる可能性があります。
また、上記の通り意見陳述のみでは証拠にならないという規定があるので、被害者の処罰感情を証拠化してもらうことや、被告人質問についての方針などを検察官と話し合うようにすると、より良いでしょう。
さらに、量刑を決めるのは裁判官であり、心情に関する意見陳述や証人尋問・被告人質問などについても十分表現内容を検討する必要があります。そのような心情に至った具体的経緯がよく分かるように詳細に意見陳述を行うほか、意見陳述の時間を十分に確保させることも重要になってきます。さらに、表現についても、過激になりすぎたり過小になりすぎたりしないようにする必要が出てきます。
被害者御本人だけで参加すると、やはり公判の順序や、表現の内容や加減が難しくなるように思います。表現内容や、弁護士の有無によって十分な活動ができるかどうかには差が出るように思います。量刑や裁判長への印象が量刑に影響したのでは、とも思える事件もあるように思います。
4 まとめ
被害者参加での対応にお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。
御本人のみでも検察官が十分サポートしてくれますが、どうしても限界があるように見受けられます。弁護士がサポートすることで、納得のいく量刑判断が得られるかも知れません。
相談に関しては無料ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
加害者との被害弁償・示談交渉の進め方について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします

犯罪の被害に遭ったとき、加害者との被害弁償・示談交渉はどのように進めていけばいいのでしょうか?
知り合いとの金銭トラブルの延長上の事件などであれば、お金や物さえ戻ってくればいいという人もそれなりに多いかと思います。しかし、見ず知らずの人に無理矢理わいせつな行為をされた場合等に関しては、すぐに示談をしようと考えるとは限らず、どのように交渉を進めていったらよいのか分からない人も多いと思います。
そこで今回は参考事例を基に、示談交渉の進め方を紹介していきたいと思います。
今回は、不同意わいせつ致傷事件の事例を参考にして解説します。
1 参考事件
愛知県内に住む女性のAさんは、ある日の夜10時頃、会社から帰るために道を歩いていたところ、いきなり暴漢に襲われ、胸を揉まれる、服の中に手を入れられる、抱きつかれるなどのわいせつ行為をされ、何とかそこから逃げ出すために抵抗をしました。何とか暴漢から逃れることはできましたが、暴漢から離れるときに転んでしまい、膝に全治2週間程度のケガをしてしまいました。Aさんはすぐに警察に通報したので、付近の防犯カメラなどがスムーズに回収でき、暴漢は逮捕されました。
暴漢が逮捕された知らせが入ってから2日後、暴漢の弁護人から、賠償金の支払いや示談の話がしたいと言われました。弁護人からは、今すぐに示談に応じてくれるのであれば示談金として100万円を支払いたい、というようなことを言われています。
示談に応じると今後どうなるかよくわからなかったのもあり、Aさんはインターネットで弁護士を検索して相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 示談で得られるもの
そもそも示談書に記載される条項は、①事実の特定②示談金③接触禁止④事件について示談後にお互い新たな主張をしないこと⑤犯人を許すこと、等の条項などが盛り込まれることが多いです。このうち、被害者側が示談をすることによるメリットは、②あるいは③になってくるでしょう。接触しない、ということについては当然と言う方もいますし、そもそも確実に担保されるかどうかもわからないという方も多いと思うので、明確な示談のメリットとしてはやはり示談金ということになるかと思います。本来、損害賠償金を得るためには民事裁判を起こして勝訴判決を得て、加害者の財産に執行をかけて回収をする等しなければならないわけですが、その損害賠償を示談の形ですぐに実現できるのも示談で得られる大きなメリットの一つです。
以下は、ひとまず、示談さえできれば基本的に示談金は直ぐに手に入ること、を示談の最大のメリットとして話を進めていきます。
3 注意したい点
まず注意したいのは、加害者側からの最初の示談金の提示は低めの金額に止まることが多いことです。実際に犯人側にお金があるか、誰がお金を出すかなど事情は様々で、相手方の弁護士が被害者側をだまそうとしていると言い切ることはできないのですが、本当に妥当な金額なのかはよく考えた方がよいです。
次に注意したいのは、示談の際に上記⑤の犯人を許す条項の追加を求められることが多い事です。たしかに、⑤のような条項を入れることによって、示談金の上乗せや、③のような条項の充実を図ることはできますが、犯人を処罰したい気持ちが強い場合は、⑤のような条項を入れるかどうかは慎重に考えた方がよいです。
最後に注意したいのは、犯人側から、すぐに示談をするように迫られることも多い事です。早く決めてください、と直接的に言われることはあまりありませんが、「検察官の処分もあるので」というようなことを電話口などで言われる可能性があります。それは犯人側の事情であって被害者側には何も関係ないのであり、検察官の処分期限があるのを良いことに示談金を抑えて示談も早く終わらせようという考えで言っている可能性があります。
しかし、示談が出来なければ今後も身体拘束が続く可能性が高く、刑事裁判にかけられて前科が付いてしまう可能性も高いわけですから、早めに示談をした方が示談金としては高い金額を得ることができる可能性は上がります。逆に、起訴されてしまって前科が付くことが確定したような場合、もはや今後示談の提案がなされることはなく、最悪1円も損害賠償金を得ることができなくなってしまうかもしれません。
そのため、被害者側として示談を行っていくにもタイミングを考える必要はあります。
ただし、起訴がされる前でさえあればまだ高額の示談金を支払うメリットはありますから、示談金を得たい気持ちが強くてもすぐに示談に応じる必要性は比較的薄いです。また、今回のような不同意わいせつ致傷の事案だと、示談をしない場合刑務所に行かなければならない可能性もありますから、裁判になった後でも比較的高額の示談金を得られる可能性があります。
上記のように、示談金の金額と、加害者側の処罰や身体拘束の長さについてはある意味トレードオフの関係にあります。示談金と、加害者側の事情については、刑事事件の知見が無ければ精度の高い計算を行うことは難しいでしょう。また、加害者側の弁護士も、刑事事件の様子を見て示談の動きを決めるわけですから、実際の事案に即した示談戦略は、刑事事件の経験が多い弁護士の方が精度が高くなると言えます。
4 弁護士による被害者支援
本件では、上記のように示談が無ければ加害者が刑務所に行く可能性が高い事件であると言えます。
そのため、比較的早い段階で示談に応じることで示談金の上乗せを狙っていくのか、あるいは示談のタイミングを遅らせて示談金と処罰のバランスを図っていくのか、というところがポイントになるかと思います。
多くの示談金を得たいのであれば早い段階から密な示談交渉を行い、バランスを重視するのであれば示談のタイミングを見極める方にエネルギーを注ぎます。
もちろん、被害者であれば、示談金でも処罰でもどちらも妥協したくない、トレードオフを受け入れるなどおかしい、というお気持ちになるのも十分わかります。当事務所では、経過に合わせて説明も詳細に行いますし、出来る限り示談金も処罰も最大限のものが得られるように尽力いたしますので、安心してご相談ください。
5 最後に
性犯罪その他の犯罪に遭われた方、被害弁償・示談交渉の進め方がよくわからない方、自分で事件の対応をするのがつらい方、示談をするなら納得いく条件で示談をしたい方、そもそも示談をすることが良いのかどうか分からないという方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。そもそも、トラブルに巻き込まれたために頭が整理が出来ておらず、何をしたらよいのかという考えにも至らない方もいらっしゃると思います。そのような場合でも、最大限お話を聞いて、最適な解決策を提案いたします。
相談に関しては無料ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
不同意性交等致傷、不同意わいせつ致傷での立件
自分や家族が不同意性交等致傷や不同意わいせつの被害に遭ったけれども、特段ケガをした形跡は無い。しかし、事件に遭ってから生活は変わってしまい、場合によっては人生が狂ってしまったとも言えるような状況になってしまった。このように感じている被害者の方も多いのではないかと思います。
今回は、不同意性交等で精神的な症状が出た場合について解説していきます。

1 参考事件
愛知県小牧市内に住む女性のAさんは、ある日、会社の上司の男性Bから、会社内の空き部屋に呼び出され、「応じなければ会社にいられない」等とも脅されたため、断り切れずに性交をしてしまいました。
その後、Aさんは精神や身体の不調を感じ、会社を休職するような事態になりました。不審に思った会社が動いたため、上記のような性行為の事実が明らかになり、Bは無期限謹慎を受けることになりました。Aさんが警察に被害届を出すと、数日後にBは警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 法律上の論点
上記事例については、Aが「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」「により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」を認識しつつBがAと性交を行ったのはほとんど明らかであるため(刑法177条1項,同法176条1項8号)、捜査や公判でも大きな障害なくBを不同意性交等罪で処罰してくことができるでしょう。不同意性交等罪で立件するだけであれば、警察や検察が捜査や起訴をためらうようなこともないでしょう。
問題としては、上記の行為によって、精神的な症状が引き起こされ、不同意性交等致傷罪での立件が可能であるか、というところになります。不同意性交等致傷罪での立件には、不同意性交等と精神的症状の因果関係が必要になります。精神的症状については、外から確認することができないので、不同意性交等との因果関係の立証が困難になる傾向があります。
3 不同意性交等致傷での立件のメリット
まず、不同意性交等致傷での立件のメリットとしては、加害者を重い罪で罰することができる事になります。不同意性交等のみでの処罰だと、法定刑は5年以下の懲役ですが(刑法177条1項)、特に初犯であれば酌量減軽がされることもあり、実際には懲役4年程度になることもあります。示談もしないで執行猶予になることまでは考えにくいですが、被害者側の立場からしたら納得はしづらいでしょう。
ただし、不同意性交等致傷については法定刑が6年以上の懲役あるいは無期懲役となります(刑法181条2項)。無期懲役になるケースは稀でしょうが、7年から8年程度の懲役となるケースは珍しくありません。被害者側の立場からすれば、ある程度は納得もしやすいでしょう。
もう一つの大きなメリットとしては、損害賠償金や示談金が高額になる傾向にあることです。民事裁判などで認められる損害賠償金も大きくなるのはもちろん、処罰が重くなるので高額な示談提案も出やすくなります。
4 不同意性交等致傷が認められるハードル
精神的な症状で不同意性交等致傷が認められる場合、代表的なものがPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。これに関しては、事件を公訴時効にかけないためにPTSDの発症を認めた可能性もある裁判例(https://www.sankei.com/article/20220908-JNEVNBF2DRNILLIJTR3LI46ITY/)があるなど、訴訟上の都合から認められるのではないかという疑いもあるのですが、基本的には致傷結果の証明も厳格に行われるべきであるとされています。とくに、PTSDでの不同意性交等致傷については、先述の通り外見から判定することも出来ないので、立証のハードルは高くないと言えます。具体的に立証のハードルといえる主なものは以下です。
・具体的な基準があること
PTSDになった原因と思われる出来事の重大性などのほか、実際の生活や認知の状態にどのような変化があったのかが問題となります。診断基準が具体的に定められており、その診断基準に当てはまるかどうかがまず問題になります。
・審理が長期化すること
PTSDになったことや、事件との因果関係の証明のために、実際に診断や鑑定に当たった医師が法廷で証言する必要が生じることが多いです。また、事件が裁判員裁判になるほか、加害者側からの控訴がされる可能性も高くなります。
・被害者として尋問に立たなければならなくなる可能性も高くなること
具体的にどのような状況の変化が起きたのかなどについて、被害者様の調書等が不同意とされることも多いです。刑事訴訟法改正が進んでおり、法廷での証言についてはだいぶ負担が少なくなるようにはなっておりますが、それでも負担が大きいのは変わらないと言えます。
5 不同意性交等の被害に遭った方は一度弁護士にご相談ください。
不同意性交等の被害に遭われた方、納得いく処罰を実現し、納得のいく損害賠償金の獲得を目指されたい方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。
もちろん、トラブルに巻き込まれたために頭の整理が出来ておらず、何をしたらよいのかという考えにも至らない方もいらっしゃると思います。そのような場合でも、最大限お話を聞いて、最適な解決策を提案いたします。
相談に関しては無料ですので、是非一度お気軽にご相談ください(https://higaisya-bengo.com/soudan/)。
交通事故被害でも弁護士費用特約は使えます!
交通事故の被害に遭った場合、弁護士費用特約が使えないと勘違いをしている方が多くいらっしゃいます。弁護士費用特約についてメリットや利用時の注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」とは、交通事故にあったときに弁護士に解決を依頼した場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。
被害者の方ご自身の自動車保険に付帯しているもののほかに、ご家族の自動車保険に付帯しているものを利用できる場合や、火災保険に付帯している場合もありますので、交通事故被害に遭った場合には、ご自身の自動車保険だけではなく、ご家族の自動車保険や火災保険についても確認してみましょう。
弁護士費用特約を利用する場合、保険会社から弁護士を紹介してくれることが多いようですが、必ずしも保険会社から紹介された弁護士でなければ特約が使えないというわけではありません。
ご自身で信頼できる弁護士を探して依頼して弁護士費用特約を利用することもできますし、ご自身で弁護士をお探しになる方が解決に向けた安心感や納得を得られやすくなります。
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約の一番大きなメリットは、交通事故被害に遭った場合に、弁護士費用を負担することなく解決に向けた活動を弁護士に依頼することができるという点にあります。
保険を利用する場合に懸念されることとして、「翌年度以降の保険等級が下がって保険料が上がってしまうかもしれない」ということがありますが、弁護士費用特約を利用しても、翌年度以降の保険等級には何ら影響しません。
通常、弁護士に法律相談をする場合、1時間1万円(別途消費税)という料金で法律相談を受け付けている法律事務所がほとんどです。
弁護士費用特約を利用すれば、この法律相談料も特約の適用範囲となるため、実質無料で法律相談を受けることができます。
また、多くの弁護士費用特約では、法律相談の回数に制限を設けておらず、保険金支払いの上限を設けていることが多いため、保険金支払いの上限までであれば、法律相談を繰り返すこともできますし、解決に向けた活動に関する報酬なども保険金上限内であれば費用負担は必要ないということになります。
弁護士費用特約利用時の注意点
弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社に事前に連絡を入れておく必要があります。
保険会社の事前承認が必要なためです。
これを忘れてしまっていると、あとから弁護士費用特約で弁護士費用を保険会社に請求しようとしても断られてしまう可能性があります。
また、弁護士費用特約の内容も保険会社によって様々です。
たとえば、保険金支払額の上限として300万円ほどの場合がほとんどですが、保険会社によってはそれよりも少ない額までしか特約が適用されない場合もあります。
また、弁護士費用の計算方法に制限を設けている場合もあります。
弁護士費用の計算方法としては、①着手金や報酬金の定めがあり、それに基づいて計算する方法、②業務時間に応じて計算する方法(タイムチャージ制)の大きく2種類があります。
②のタイムチャージ制については、保険会社によってそもそも弁護士費用特約の対象外とされていたり、タイムチャージの時間に上限を設けている場合もあります。
そのため、金額の上限には達していないものの、タイムチャージの時間が超過してしまい、超過した時間分の弁護士費用については特約が適用されず自分で費用を支払わないといけなくなる場合もあります。
さらに、弁護士費用の全てが特約によってカバーされるわけではありません。
書面の作成料などについて、保険会社によっては負担の対象外とされてしまっている可能性があります。
そのため、保険契約書の内容をしっかりと確かめたり、保険会社に事前に連絡を入れる際に、依頼しようとしている弁護士の報酬基準などを保険会社に説明して特約の適用範囲内かを確認しておくことが必要です。
交通事故の被害に遭ったら
交通事故の被害に遭われた場合、多くは加害者側の保険会社から治療費や慰謝料などの支払がなされます。
しかし、過失割合に争いがあったり、加害者が任意保険に入っていなかったりした場合、加害者側に賠償を求めるために被害者の方が弁護士に依頼して交渉をしていく必要が出てきます。
その場合に非常にメリットが大きいのが弁護士費用特約です。
ですが、弁護士費用特約が利用できるのかどうかや、そもそも弁護士に依頼したら加害者からどれくらいの賠償がとれるのかなど不明な点が多く不安を抱えてしまうことも多いでしょう。
そういった場合には、初回相談無料の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください(https://higaisya-bengo.com/soudan/)。交渉にあたっては、加害者の刑事手続がどこまで進んでいるかも重要になってきますので、早期に弁護士に相談することが推奨されます。加害者側の刑事手続については、こちらの記事もご参照ください(https://osaka-keijibengosi.com/keiziziken_flow/)。
まず弁護士に相談して、今後どうしていったらよいのか、弁護士費用特約が利用できるのかなどを知ることで不安が少しでも解消できます。
性犯罪被害者は刑事裁判の法廷でも保護されます
性犯罪の被害に遭ってしまった場合、刑事裁判の法廷で証言しなければならなくなることは、被害者の方にとって大きな負担となります。
実際に、法廷での証言を回避するために被害届を出すことを断念したり、示談に応じざるを得ないということもあります。
しかし、最近は法改正によって、性犯罪被害者が法廷で証言をする負担が緩和される傾向にあり、証言のうち主尋問にあたる部分を、事前に録画した動画で対応することができるようになりました。

対象者
令和5年に行われた刑事訴訟法の改正によって、性犯罪被害者が証言する負担が一定の条件のもとで緩和されることになりました(刑事訴訟法321条の3)。対象となるのは、以下に記す性犯罪被害者等になります。性犯罪被害に限定されるわけではありません。
・不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、不同意わいせつ等致死傷、十六歳未満の者に対する面会要求等、わいせつ・結婚目的等略取及び誘拐、わいせつ・結婚目的人身売買、被略取者引渡し等、強盗・不同意性交等及び同致死の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
・児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の罪の被害者
・犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
証拠提出方法
対象者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体を提出して行うことになります。
その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限られます。
供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置、が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であって、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときに、証拠とすることができます。性犯罪被害であれば無条件に認められるわけではないことには注意が必要です。
反対尋問
この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければなりません。
つまり、反対尋問の機会が設けられる、加害者側の弁護人から反対尋問を受けることになります。反対尋問も含めた公判(刑事裁判)の流れについては、こちらもご参照ください。https://tokyo-keijibengosi.com/kouhan_flow/
しかし、法廷では被害者の名前等の個人情報は読み上げられません。
他にも、被害者を衝立で囲って加害者や傍聴人等から見られないようにされます。
もしくは、裁判所の別の部屋からリモートで参加して、やはり加害者や傍聴人等から見られないようにされます。法廷における犯罪被害者保護の具体的な内容については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/hanzaihigai_himitu/
今後の刑事手続についてご不安ならぜひご相談を
性犯罪被害に遭ってしまった場合、今後の刑事手続に対して大きな不安を感じるはずです。
加害者はきちんと逮捕・勾留されるのか、起訴されるのか、有罪になるのか、といったことについて心配になると思います。
加害者から賠償はなされるのか、お金を受け取ったら刑事罰が小さくなるのか、といったことについても考えることが多いです。
同時に、被害者自身が、捜査で取調べを受けるのか、裁判となったら法廷に立たなければならないのか、個人情報やプライバシーが漏れてしまうのではないか、などについても大きな不安を感じることが多いです。
もしくはより積極的に、刑事裁判に被害者参加を希望し、被害者の想いを法廷で主張していきたいという人もいると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、犯罪被害者支援に精通している弁護士が多数所属しております。
性犯罪被害者の方々のご不安に対して、一つ一つ丁寧にご説明いたします。
まずは気軽にご相談してください。
被害者の方だけでなく、ご家族の方も一緒に相談にお越しいただけましたら、ご一緒に説明いたします。
犯罪被害の告訴を検討中の方はご相談ください
犯罪被害に遭ってしまった場合、捜査機関に対して犯罪被害を受けたことを報告する被害届を提出するだけでなく、犯人への刑事処罰を求める告訴を行うこともあります。今回はこの告訴について、制度や告訴が必要となる犯罪、告訴を行うにあたってのポイントについて解説します。

<告訴権者>
犯罪被害に遭ってしまった方は、告訴をすることができます。
名誉毀損罪・侮辱罪に関しては、告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行うことになります。
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができます。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができますが、被害者が告訴をしない意思を明示しているのであればすることができません。
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができます。
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができます。
名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができますが、被害者が告訴をしない意思を明示しているのであればすることができません。告訴については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/hanzaihigai_attabaai_taisyo/
<親告罪>
親告罪とされる犯罪については、告訴がなければ公訴を提起・起訴することができません。
親告罪としては、秘密漏示罪、過失傷害罪、未成年者略取誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪・詐欺罪・恐喝罪・横領罪、毀棄・隠匿罪、等があります。
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができます。
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができません。
ただし、名誉棄損罪・侮辱罪について外国の代表者が行う告訴、日本国に派遣された外国の使節に対する名誉棄損罪・侮辱罪につきその使節が行う告訴については、告訴期間の制限はありません。
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼしません。
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができます。
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができません。
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生じます。
告訴とその取消は、代理人によりこれをすることができます。親告罪については、こちらの記事もご参照ください。https://sapporo-keijibengosi.com/kokuso/
<捜査機関の対応>
告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければなりません。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければなりません。
司法警察員は、告訴を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません。
<告訴はしっかりとした手続により行わなければならない>
告訴はとにかくすればいいというわけではありません。
告訴をされた警察としても、告訴された事実が具体的にどういうことなのか、本当なのか、犯罪として成立するのか、どのような経緯や背景があったのか、証拠としては何があるのか、今後どのような捜査をしていけばいいのか、等がある程度検討できるようにしなければなりません。
いい加減な告訴をしても、警察としてもどのように対応すればいいか分からず、結局は捜査がまともに進まずに犯罪被害者にとって悪い結果になる可能性があります。
犯罪被害に遭ってしまった方は、告訴についてぜひ弁護士に相談してください。
きちんとした手続きで告訴を進めていき、捜査機関と話し合いながら、犯人の処罰を求めていくことになります。
【報道解説】盗撮未遂容疑の警察官を不起訴処分 女子中学生スカート内にスマホ疑い
警察官が女子中学生のスカート内にスマホを差し入れ盗撮しようとした事件について、不起訴処分となったという報道がありました。なぜ不起訴処分となったのかなどについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道の内容】
京都地検は、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)と京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された警察官Aについて、不起訴処分にした。理由は明らかにしていない。
Aは、京都市左京区の京阪出町柳駅で、スマートフォンを女子中学生のスカート内に差し入れ、撮影しようとしたとして、京都府警下鴨署に逮捕された。逮捕時の調べに対し容疑を認めていた。
(京都新聞令和6年2月14日インターネット記事https://news.yahoo.co.jp/articles/4bc2b7bed8a8011b6cd81fa1eb77038fb33701a5より抜粋。一部改変)

性的姿態撮影処罰法とは
性的姿態撮影処罰法とは、令和5年7月13日より施行された新しい法律です。
盗撮事件の増加に伴い、これまで各都道府県の迷惑行為防止条例によって規制されていた盗撮行為について、より罰則を強化して取り締まりを充実させるために制定されました。
これまでは、盗撮場所が分からなかった場合には条例は各都道府県によって違うため、処罰ができないことがありました。
また、各都道府県によって条例の内容が違うため、条例では処罰できなかったり、軽い刑罰しか定められていなかったりといった問題がありました。
法律になったことで、どこで行った盗撮でも罪に問うことが可能となり、刑罰も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金というより重いものとなりました。
さらに、本件のように、未遂罪についても処罰することができるようになりました。
なぜ不起訴となったのか
今回の事件では、Aは自分の行為を認めています。
そのため、通常であれば罰金などの刑罰を受けることになると考えられます。
しかし、今回は不起訴となっています。
不起訴となる場合にもたくさんの場合がありますが、今回の事件では、①嫌疑不十分、②起訴猶予のいずれかによって不起訴となっていると考えられます。
①嫌疑不十分とは、犯罪を証明するための証拠が少なく、間違いなくAが性的姿態等撮影未遂にあたる行為を行ったという証明ができなかったという場合です。
しかし、今回の事件では、Aは自らの行為を認めていますし、逮捕されていることから盗撮しようとしたという証拠は十分にあったと考えられるため、①嫌疑不十分のために不起訴になった可能性は低いと考えられます。
起訴猶予とは
②起訴猶予とは、犯罪の証明はできるが、いろいろな事情から判断して起訴をいったん見送ったというものです。
色々な事情としては、成立する罪の軽重、事件内容の軽重、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、被疑者の反省、社会的影響の軽重など様々な事情が考慮されます。
今回は盗撮事件ですので、被害弁償の有無や被害者の処罰感情、被疑者の反省などが考慮されたと考えられます。
つまり、おそらくAは被害者である女子中学生(未成年者なのでその両親)との間で示談を締結していると考えられ、また、警察官の職を失っていると考えられることから不起訴となったと思われます。
公務員によって被害を受けた場合
本件のように公務員から被害を受けた場合、加害者である公務員側から示談交渉を持ち掛けられることが多くあります(示談については、こちらのページもご覧くださいhttps://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/)。
なぜなら、国家公務員であれ地方公務員であれ、犯罪を起こして起訴されてしまうと、たとえ執行猶予がついたとしても失職してしまうからです。
また、警察官や消防士、教職員などについては、一般の公務員よりも懲戒処分の指針が厳しく定められており、司法判断つまり刑事処分の如何によって懲戒処分の重さが決まることになっていることが多くあります。
そのため、加害者が公務員の場合には、不起訴や略式罰金の処分を勝ち取るために示談交渉を持ち掛けてくるのです。
示談を受ける場合のメリットは、賠償を早期に受けることができ、接触しないなどの条件を付けることができることが挙げられます。
一方デメリットとしては、示談を受けることにより加害者の刑事処罰が軽くなったり、不起訴となって刑事処罰を受けることがなくなったりすることが挙げられます。
その他、事案によって示談を受けるメリットデメリットがありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
不同意性交等罪での示談について
犯罪被害に遭って警察に通報し、警察が事件として扱ってくれることになりました。警察に通報したところでは犯人が誰なのか分かりませんでしたが、警察の懸命な捜査の結果犯人が分かり、犯人が検挙されました。犯人は逮捕されているようなので、犯人が直接被害者とやり取りすることはできないようですが、逮捕されて間もなく、検察庁から電話があって、犯人の弁護士にだけ被害者の連絡先を教えてよいかと質問されました。
今回は、加害者側の弁護士から連絡先を教えてほしい、などと言われたときの対応と、結果の見通しについてお話しします。

1 参考事件
愛知県名古屋市北区に住む女性Aさんは、事件当時高校生でした。
ある日、部活動が遅くなって、夜に最寄駅から自宅までの道を歩いている最中、加害者の男からいきなり襲われ、人目につかないところまで引っ張られて、殴る蹴るなどの暴行のほか、男性器を女性器に挿入されそうになる、その様子を携帯電話端末で撮影されるなどの被害に遭いました。Aさんは、加害者との面識は一切ありませんでした。
Aさんが自宅に帰宅して夕食を食べるものの、このような経緯から制服が非常に汚れていたこと、夕食時の様子がおかしかったことなどから、Aさんの母親Bさんが、Aさんに何があったのか尋ねると、Aさんは先ほどのような経緯を話しました。これは大変だと思ったAさんとBさんは、事件当時来ていた制服などを持ってすぐに最寄りの警察署に向かいました。
その後、Aさんは深夜まで及ぶ取調べを受け、身体からも犯人のDNAを採取するために検体の保存が行われました。数日後にもまた数時間にも及ぶ取調べを受けました。防犯カメラ映像や、DNA型の文政期が上手くいったことから、先ほどの加害者が逮捕されました。
逮捕後すぐに、検察官から「加害者側が被害弁償をしたいということなので、加害者の弁護士だけにBさんの電話番号を教えても良いか」と言う電話が来ました。(この参考事件はフィクションです。)
2 法律解説
本件の加害者の行為については、不同意性交等罪にあたることはほとんど争いないでしょう。
また、不同意性交等の様子を撮影しているので、性的姿態等撮影罪も成立します。今回は、加害者弁護士から接触の試みがあったときの対処を開設するのがメインなので、詳しい条文解説は省略します。不同意性交等罪の解説は、こちらの記事もご参照ください。https://keiji-bengosi.com/gokan_kyoseiwaisetsu/
本件の加害者の行為については、示談や弁償等が無ければ相当厳しい処分になるのは間違いなさそうです。加害者や、加害者の弁護士としても、何とか示談や弁償をしたいという気持ちが高まっていると思われます。
3 対処法・弁護士によるサポート
まず考えなければならないのは、そもそも加害者の弁護士に電話番号を教えるかどうかです。基本的に、弁護士には守秘義務があるため、加害者本人やその家族に被害者の電話番号を教えることはないと考えられます。守秘義務違反には弁護士業務停止を含む相当重い懲戒処分が予定されるので、弁護士から加害者に被害者のプライバシー情報が漏れることはないのですが、どうしても心配ということであれば電話番号を教えないようにするとか、代理人の弁護士を依頼してその弁護士の連絡先を伝えてもらうということが考えられます。
次に考えるべきことは、示談金額及び誓約条項です。示談金額については、法律で金額が決まっているわけではないので、弁護士や加害者によって提示額も様々となり、妥当な金額であるのかどうか判断が難しい可能性があります。弁護士に依頼することによって、より打倒で納得できる金額になるように交渉することができる可能性がありますし、依頼をしないにしても、妥当な金額かどうかの回答をすることはできます。また、その他示談条件についても、一定の場所を一切通らない、一定の場所に近付かない等の内容が考えられます。このような条件も、弁護士や加害者によって提示内容は様々ですし、加害者側も被害者側の事情をよく知っていることは考えにくいので、最初から被害者側が納得できるような条件が提示されるとは限りません。やはり、その他示談の条件についても、弁護士に相談・依頼をすることで納得できる妥当な内容に近付く可能性が高くなります。
最も重要なのが、被害者の刑事処分を望まないような内容を示談書に記載するかどうかです。
被害者の刑事処分を望まないような内容の条項を、一般的には宥恕(ゆうじょ)条項と呼んでいます。宥恕というのは、要するに加害者を「許す」という内容であると理解していただいて構いません。
この宥恕条項については、加害者の刑事処分を軽減するのに相当重要な意味合いを持っており、加害者側としてはできるだけ示談書に盛り込みたい条項になります。示談書に記入した以上、基本的には「やっぱり許したくない」といったようなことを後から言うことはできなくなりますので、このような条項を入れるのであればよく気持ちを整理してから入れる必要性があると言えます。また、宥恕条項を入れるのであれば、その他の条件について妥当かどうかを判断し、妥当な条件に近付けるために弁護士が果たす役割も無視できないと言えます。示談についてはこちらの別記事もご覧ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
4 最後に
以上、加害者側の弁護士から接触の試みがあったときの対処法を簡単に紹介させて頂きました。
以上でご紹介させて頂いた他にも、各条項については示談・契約でしか使わないような専門的な用語が入っていたり、個別の事件事情により必要な条項が入っていたりいなかったりすることがあります。
加害者側としては、刑事処分を軽減するために被害者側に有利な条件を受け入れてくれる可能性も比較的高いのかもしれませんが、示談書全体の効力はよく検討しないといけませんし、細かい交渉を行うのは被害者側には大変かも知れません。
いずれにしても、弁護士に一度相談をしてみるのが示談交渉において正しい判断をしていくのに役に立つことでしょう。