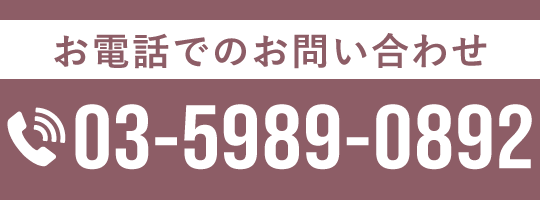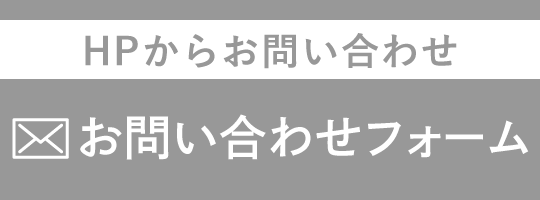自社ブランドのロゴや商品名などを勝手に使用された場合には、どういったことができるでしょうか?全く同じとは言えないけれども自社ブランド商品と間違われるようなロゴを使用された場合も含めて、商標権侵害にあたるかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
商標権とは
自社ブランドのロゴや商品名については、商標を登録して商標権を得ることが考えられます。
商標権とは、登録されている商標を使用する商品または役務について、勝手に他者に登録商標を使用されない権利ということができます。
このことを法律的には、「登録商標を使用する権利を専有する」といいます。
また、商標権は、登録商標を使用する商品または役務を指定して設定されるため、指定した商品または役務とは全く異なる商品や役務に対してまで商標権が及ぶことはありません。
商標権侵害にあたる場合
商標権を持っている人又は会社(商標権者といいます)は、商標を登録してから10年間(更新することもできます)はその商標を使用することを独占することができます。
そのため、登録商標を使用することを商標権者が了承していないにもかかわらず、商標登録の際に指定した商品や役務と同一の商品や役務に登録商標を使用された場合には、商標権侵害にあたります。
また、登録商標を使用しているのが、指定した商品や役務と同一ではなかったとしても、「類似」の商品や役務にあたる場合には、侵害となります。
「類似」にあたるかどうかの判断
「類似」といえるかどうかの判断については、特許庁が「類似商品・役務審査基準」を公開しています。(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html)
この「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているものです。
また、裁判で商標の類似が争われた裁判例をもとに、裁判上での基準をまとめると、商標の類否は、「見た目」、「読み方、呼び方」、「意味」を全体的に考察し、更に、取引の実情を考慮して、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、出所の混同が生じるおそれがあるかによって決定されているとまとめることができます。
商標権侵害への救済手続
商標権侵害への救済手段として、①差止請求、②損害賠償請求、③不当利得返還請求、④信用回復措置請求、⑤刑事責任の追及をすることができます。(詳しくは特許庁のホームページをご覧ください https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html)
①~④については、侵害された商標権を有する会社が原告となり、訴訟を提起する必要があります。
一方、⑤刑事責任の追及に関しては、警察などの捜査機関に被害届の提出等、商標権侵害の事実を申告して、捜査を開始してもらう必要があります。
刑事責任を追及するためには、捜査機関に捜査をしてもらわないといけませんが、捜査を開始させるためには被害を受けた会社から被害を裏付ける証拠の提出を求められます。
そのため、①~④の民事訴訟を起こす場合と同様に、事前の準備が必要となります。
商標権を侵害された場合には
商標権を侵害された場合には、専門家に相談して、どういった手段が採れるのか、その手段を採るためにはどういった準備が必要なのかなどをしっかり検討しましょう。
特に、同一とはいえない商品等により侵害されたと考えている場合には、商標権侵害にあたる「類似」の商品等にあたるかどうかについて、専門的な判断が必要になります。
また、訴訟をする場合には、弁護士が代理人となるかならないかで結果は大きく変わってきます。
刑事責任を追及する場合でも、捜査機関にしっかりと捜査をしてもらい、侵害者を罪に問うてもらうために、事前の準備などが必要になってくるので、早めに専門家に相談しましょう。