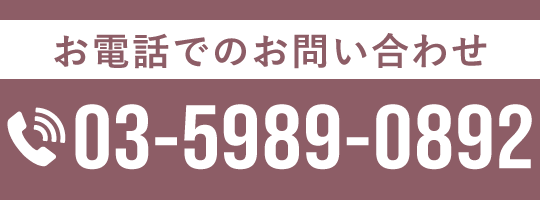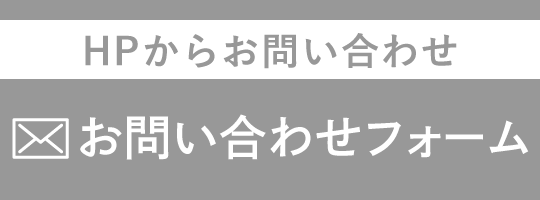このページの目次
子供が怪我をして帰ってきたときに、親としてどういった動きをするべきなのか、様々なパターンに応じての対応を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
中学生のA君が、顔に大きな痣を作って帰ってきました。
今朝学校に行く際には、そのような怪我がなかったため、お母さんはA君に話を聞くことにしました。
まずはしっかりと話を聞く
子供が怪我をして帰ってきたときには、まずしっかりと話を聞いてあげましょう。
話を聞くときは、矢継ぎ早に質問するのではなく、「その怪我はどうしたの?」という最初の質問以外は、子どもが話をしてくれるのを待ちましょう。
あまりにも、親の方から質問をしてしまうと、子どもの記憶に影響してしまい、実際の事実とは異なる記憶に改ざんされてしまう可能性があります。
たとえば、「誰にやられたの?」と聞いてしまうと、自分で転倒してできた怪我だったとしても、誰かに殴られたと言ってしまうかもしれません。
また、誰かに殴られたりして怪我をしてしまっている場合には、なぜ殴られてしまったのかとても気になると思いますが、なんで殴られたのかについて根掘り葉掘り聞いてしまうと、自分のことを良く見せようとして相手のことだけを悪く言ってしまったり、逆に自分は全く悪くないのに、自分にも悪い部分があったのではないかと不安になり、きちんと事実を話せなくなってしまう可能性があります。
そのため、寄り添う姿勢をしっかりと見せつつ、気長に子供の話に耳を傾けるように気を付けましょう。
参考:https://www.nnvs.org/wp-content/themes/hanzaihigai/images/network/pdf/otonawbsaisyu.pdf
病院に連れて行く
ある程度話を聞いたら、病院に連れて行きましょう。
顔面の怪我の場合には、脳などにも影響があることがありますので、念のため脳神経外科なども受診するといいでしょう。
また、他にも怪我をしている部分がないかもよく観察しましょう。
もし、誰かに怪我をさせられたということであれば、診断書を医師に作成してもらいましょう。
学校内で怪我をしていた場合
学校内で怪我をしていた場合、誰かに怪我をさせられたということであれば、まずは学校に相談してみるのがよいでしょう。
一時的な喧嘩だったのか、いじめを受けているのかなどを学校に調査してもらいましょう。
そもそも、怪我をしていることを学校が把握していれば、学校の聴き取り調査が行われている可能性もありますので、学校に相談することにより、より詳細な状況が分かる可能性もあります。
しかし、学校によっては、きちんと調査してくれない場合があります。
そういった場合には、学校が公立校であれば、学校を管轄している市町村の教育委員会に相談することもできます。
特にいじめが疑われる場合には、教育委員会に相談することで第三者委員会が設置されるなど、より詳細な調査をしてもらえる可能性が出てきます。
一方、私立校の場合には、教育委員会の権限が及ばないため、原則として学校内で解決してもらうことになります。
そのため、私立校の場合には、学校に相談したにもかかわらず、加害者の子どもについても保護しようとして、きちんと調査が行われなかったり、お互いに悪い部分があったとして大事にはしないようにという圧力が学校側から加えられる事例も散見されます。
そのような場合には、弁護士に相談して、学校へ働きかけてもらうなどしていく必要が出てきます。
学校外で怪我をしていた場合
学校外で怪我をしていた場合、学校に通っている生徒から怪我をさせられたのか、全く関係のない人から怪我をさせられたのかによって対応が異なります。
まず、学校に通っている生徒から怪我をさせられた場合には、学校内で怪我をしていた場合と同様にまずは学校に相談しましょう。
全く関係のない人から怪我をさせられた場合には、すぐに付近の防犯カメラなどで犯人を特定する必要が出てくるため、近くの警察署に相談しましょう。(大阪府警察の場合https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/kodomo_jyosei/20578.html)
警察署に行く際に、診断書をすでに取得している場合には、診断書も一緒に提出して、被害届を出しましょう。
警察が被害届を受理してくれたら、捜査が開始されますので、捜査の結果などを知らせてもらえるように警察にお願いしておきましょう。
警察が捜査をするにあたっては、警察から子供に対して、どういった状況だったのかを詳しく聞かれたり、再現をさせられたりします。
子供が一人で対応することが不安という場合には、保護者の立会いを認めてもらったり、事前に弁護士と契約をして弁護士に付添や弁護士に対して子供がしゃべってくれた内容を弁護士がまとめた書面を警察に提出することができます。
犯人が特定されたら、基本的に犯人を特定したという連絡が警察から入ります。
民事事件と刑事事件
警察が犯人を特定した場合には、その犯人は刑罰を受けるか否かを決める手続に乗せられます。この手続を刑事事件手続といいます。
刑事事件手続に関しては、被害者としては捜査に必要とされる範囲で協力を求められますが、それ以外では基本的に蚊帳の外に置かれてしまいます。
犯人がどのような処分を受けることになったのかについては、「被害者通知制度」などを通じて知ることができます。
また、犯人の刑事裁判に参加して意見を述べたり犯人に質問したりすることも一部の事件では可能です(被害者参加制度)。
被害者参加制度を利用するにあたっては、弁護士に依頼して、弁護士が代わりに質問したり、意見を述べたりすることもできます。
このような犯人に刑罰を与えるか否かを決める手続とは別に、直接犯人に治療費や慰謝料など金銭を請求することもできます。
このことを損害賠償請求といい、民事事件と言われます。
民事事件の場合には、直接相手との話し合いを行う「任意交渉」と裁判を通じて強制的に犯人に金銭賠償を求める「民事裁判手続」に大別できます。
いずれにしても、犯人と対峙することになりますので、弁護士を代理人として選任して、弁護士に窓口となってもらって交渉等をしていきましょう。
このように刑事事件と民事事件は別の手続ですが、刑事事件の手続の中で犯人に対して損害賠償を請求することが出来る「損害賠償命令」の制度や刑事事件と民事事件の両方を話し合いで解決する「示談」という手続もあります。
分からないことがあれば弁護士に相談を
このように、子どもが怪我をして帰ってきた場合には、様々なことを考えないといけません。
子どもの話を聞いて、今後の対応をどうするかとても不安になることでしょう。
そういったときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、法律的な解決だけでなく、話し合いでの解決やご家族のためになる解決を一緒になって考えてくれます。
どのような対応が考えられるのか、それぞれの対応についてのメリットやデメリットなど弁護士に相談することで、今後どのような対応をとればいいのかについても明確になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。