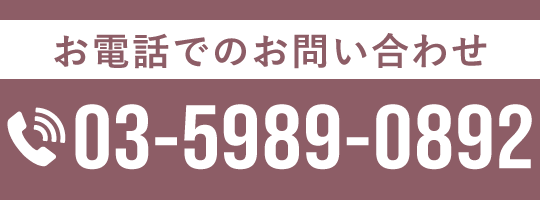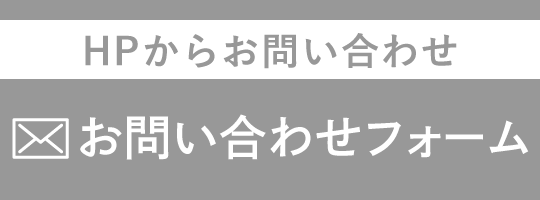児童買春の相手方となった児童は被害者といえるのか、児童買春を行った大人側から示談の申入れがあった場合にどうしたらよいのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
児童買春とは
児童買春とは、基本的に、児童(18歳未満の者)に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
簡単にいうと、18歳になっていない人に対して、お金を渡す約束や実際にお金を渡してわいせつな行為をすることだといえます。
なお、16歳未満の児童に対して、お金を支払ってわいせつ行為を行った場合、児童買春ではなく「不同意わいせつ」(性交渉があれば、「不同意性交等」)という別の罪が成立することになりますので、実際には16~17歳の児童に対して行った場合のみが児童買春となります。
児童買春の相手方となった児童は被害者といえるか
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律によって禁止されています。
同法は、「児童の権利を擁護すること」を目的としており(同法1条)、日本における児童全般を保護することを目的としているといえます。
そのため、児童買春の相手方となった児童を個別に保護しているわけではないため、厳密にいうと、児童買春の相手方となった児童は法律上の「被害者」とはいえないことになります。
児童買春を行った者から示談の申入れがあった場合
児童買春を行った者から示談の申入れがあった場合には、どのように対処すべきでしょうか。
まず、法律上の被害者ではないとしても、児童の無知に乗じて買春行為を行ったといえるでしょうから、不法行為にはあたるといえます。
また、児童の保護者からすれば、親の保護下にある児童の身体を侵害したといえるでしょうから、親としてもその責任を児童買春を行った者に問うことは可能と考えるべきです。
そのため、「示談」という言い方が正しいかどうかは別として、賠償を受ける権利はあると考えることができます。
もっとも、児童買春の相手方となった児童の同意があることが前提となる犯罪ですので、賠償金はこの側面を考慮されて判断されることになります。仮に、児童の同意がなければ「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」となります。
示談する場合のメリット、デメリット
示談する場合のメリットとしては、①早期に金銭賠償を受けられること、②条件を付けることができることが挙げられます。
相手方に金銭賠償を求める場合、損害賠償請求訴訟を提起する必要がありますが、民事裁判は時間がかなりかかる上、損害の発生と損害額などの立証を訴えた側がする必要があり、労力もかなりかかります。
特に、児童買春の相手方となった児童の親が訴える場合、そもそも損害が発生しているといえるのかも問題となるため、立証活動は弁護士に依頼して行うことになり、費用もかかります。
示談であれば、そういった裁判を行う前に金銭賠償を受けることができるため、立証責任も発生せず、早期に金銭賠償を受けることができます。
また、民事裁判の判決では、「○○円を支払え」という内容のみが記載されるため、接触を禁止したり、口外を禁止したりといった条件を付けることができません。
今後、子どもに接触してほしくない場合など、安心を得るためには、条件を付けられる示談を選ぶことにメリットがあります。
示談する場合のデメリットとしては、児童買春をした大人が罪に問われなくなったり、刑罰が軽くなる可能性があることが挙げられます。
児童買春の相手方となった児童は、上述のとおり、法律上の被害者とはいえませんが、それでも実際に対象となった児童や親が許していたり、賠償を受け取っていたりすることは、有利な事情として考慮されます。
必ず不起訴になったり、刑罰が軽くなったりするということはありませんが、そういったこともありうるということは考慮に入れておくべきです。
児童買春の相手方となった児童の処分
児童買春の相手方となった児童については、罪に問われることはありませんが、補導の対象となったり、場合によっては、少年審判を受けることになる場合があります。
何件も児童買春の相手方となっていたりする場合には、虞犯少年として、少年審判を受け、少年院送致となる可能性もあります。
犯罪となっていないからといって何もしないのではなく、警察の捜査や家庭裁判所の調査を受けることになった場合には、弁護士に早期に相談するのがよいでしょう。