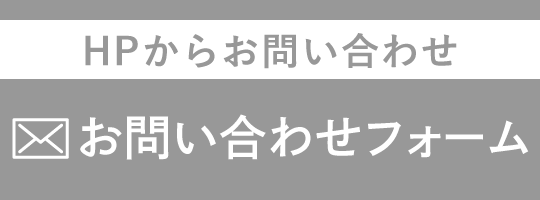不自然な支払いが繰り返されていたり、書面もないのに莫大な額の金銭の動きがあったりすると、会社のお金が不正に使用されている可能性があります。このようなときはどうすればよいでしょうか
このページの目次
会社内における不正行為への対応
犯人・被害の特定、調査
会社内で不正が生じた場合、被害の継続を阻止し、犯人を特定し、被害額を特定する必要があります。その際、証拠隠滅などされないよう、調査を進める必要があります。関係のある部署の既存メンバーにアクセスを禁じるなどの対応も必要となるでしょう。会社内での権限や事務手順、金銭の流れなどから、犯人を絞り込むことが期待できます。
犯人が自ら不正の事実を認め、休職等により現場を離れ、調査に協力してくれるのであれば、被害の継続の阻止や、犯人や被害の特定は進むでしょう。
一方で、不正を行ったと十分疑える証拠があっても、本人が自分はそのようなことをしていないと反論する可能性もあります。その場合、証拠隠滅がされないよう調査を進め、反論を考慮してもやはり犯人だといえる証拠があれば、弁護士に相談したり、警察等の捜査機関による捜査を求めることを検討する必要があります。
時効の問題
不正を行った犯人や被害額が特定できても、すべての被害金額を回収できるとは限りません。不正から時間が経っている場合は、時効の問題が生じるため、早急に対応する必要があります。
民事においては横領等の不正も不法行為であり、会社側は不正をした者に対し損害賠償請求権を有します(民法第709条)。これは損害および加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間、行使しなければ時効によって消滅します(民法第724条第1号第2号)。20年以上前の不正については請求することはできなくなります。また、損害の実態や不正をした者を把握しても、返還交渉中に時効が成立する可能性がありますので、債務を承認させたり(民法第152条第1項)、訴えを提起して裁判上の請求をする(民法第147条第1項第1号)など、時効が完成しないようにする必要があります。
刑事においては、時効期間はより短くなっています。業務上横領や電子計算機使用詐欺など長期10年の懲役という重い罪が成立する場合であっても、公訴時効は7年です(刑事訴訟法第250条第4号)。したがって、7年以上前の不正使用については罪に問うことはできないのです。公訴を提起すれば時効は停止します(刑事訴訟法第254条第1項)ので、刑事処分を求めるつもりであれば、早急に警察や検察に被害を届け出て処罰を求める必要があります。
民事手続
不正を行った者に対しては不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。もっとも、裁判自体裁判費用や弁護士費用がかかりますし、時間もかかります。そのため、不正を行った者が自発的に事実関係を認めて弁償するのがもっとも負担が少なく損害を回復することができるでしょう。また、後述する刑事手続で不正を行った者に実刑判決が下されると、その者は収監されてしまうため、弁償も期待できなくなります。そのため、警察に被害届をする前に、まず相手方が自発的に支払えるよう和解(示談)交渉することが有益です。
和解の内容は和解契約書・示談書といった形で書面に残して記載するべきです。また、万が一相手方が支払いを怠ったときは直ちに強制執行できるよう、公正証書に強制執行認諾文言を記載する形にしておくのが良いでしょう。
交渉に当たっては、上記のとおり時効が完成しないように注意する必要があります。また、仕事を続けさせたり、分割払いを認めるなど、現実的に被害金額の回収が可能な内容にするのが良いでしょう。一方で、不正を行った者が弁償できない場合やするつもりがない場合、被害届や告訴など刑事手続に移行することも検討するべきです。
刑事手続
会社内の不正行為といっても、犯人の地位や立場、行為の態様によって、成立する犯罪が違ってきます。業務上横領、詐欺、電子計算機使用詐欺、など様々な犯罪が想定されます。
特に、警察に告訴をする際には、被害者側において、犯罪事実を特定する必要があります。犯人(告訴の際は「被告訴人」といわれます)が会社内においてどのような地位にあったか、どのような権限・責任を有していたか、どのような業務を行っていたか、といった事実を詳細に記載する必要があります。また、不正の証拠や、被害額を特定できる資料も同時に提出するべきです。
被害金額が100万円以上だと、不正を行った者(被疑者)が逮捕される可能性があります。被疑者が逮捕されると、続いて勾留されることが多いです。逮捕と勾留は通算して最大23日までで、それまでに検察官が被疑者を起訴するか否かを決めます。勾留期限の満期までに被疑者が被害額全額を弁償すれば処分保留あるいは起訴猶予で釈放されることはありますが、そのようなことがなければ起訴されるでしょう。起訴の際の被害額は、検察官が証拠により特定できた金額、時効が成立していない罪についての金額となります。そのため、会社自身が特定した被害金額全てについて起訴されるとは限りません。
起訴された被告人が事実関係を認めている場合、公判における審理は1回で終わり、次回で判決となることが多いです。被害金額が500万円以上で弁償できていないと、前科がなくても実刑となる可能性があります。
一方で、被告人が事実関係を争うと、公判は長期化する可能性があります。経理担当者や役員が証人として出廷し、被告人の弁護人から反対尋問を受けることもあります。
税務上の処理
不正を行われた結果、会社のお金が減ったことになりますが、税金は全く変わらず課せられるのでしょうか。
不正利用により会社に損失が発生していますので、当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するとされています。一方で、これにより不正を行った者に対して損害賠償請求権を有することになるため、これを益金として計上することになります。この損害賠償請求権は相手方との和解等による合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入するとされています(異時両建説)。
もっとも、不法行為の相手方が会社外の者(「他の者」)ではなく会社の役員や使用人である場合は、損害賠償請求権も損失が発生した事業年度の益金に算入するという説もあります(同時両建説)。
弁護士への相談
このように、会社の金が不正に使用されていた場合、被害について調査するにも回復するにも大変な労力が必要となってきます。これを会社の通常業務を行いながら進めていくというのは困難です。
こうした場合、早期に弁護士に依頼することも考えるべきでしょう。
弁護士に依頼することで、会計資料の調査や関係者のヒアリングを行い、犯人や被害額の特定を進めることができます。
その後は、犯人と和解交渉をして被害金額の回収を図ることができます。任意に弁済できなかった場合、訴えを提起し、判決を得て強制執行をすることもできます。
また、犯人の刑事処分を求めるのであれば、告訴も行うことが考えられます。特に、告訴を行う場合、犯罪事実の特定が必要となります。この作業は事実の調査だけでなく、事実を法的に構成する必要があります。これは法律の専門家である弁護士がもっとも適切に行うことができるでしょう。
起訴されても被告人が否認している場合、会社の役員や他の従業員が証人として出頭を求められることがあります。その際、検察官が証人予定者に証人テストを行いますが、弁護士の方でも会社の方々と事実関係を整理して、適切に証人尋問に対応していくことができます。
税務上の問題は税理士がやることだと思われがちですが、弁護士が法律問題を整理することで、より適切に処理することができます。
このように、弁護士は会社内の不正事件について最初から最後まで強力に支援することができます。
会社内で不正の疑いがあるときは、無理に自分たちだけで処理しようとせず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。